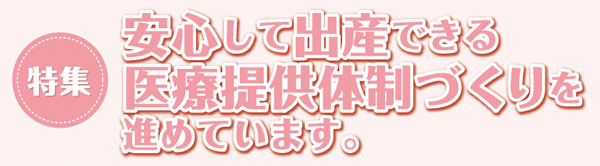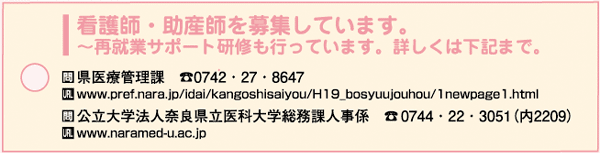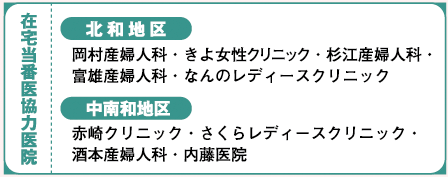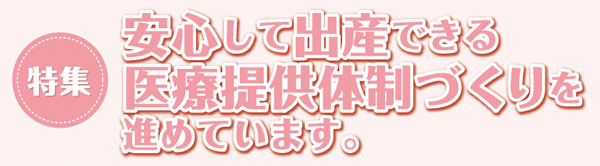 |
 |
一昨年の大淀での妊婦死亡事故と、昨年8月、搬送先の医療機関の選定に時間がかかり、搬送中に妊婦が死産するという事故がおこり、県民の皆さまに妊娠・出産について大きな不安を与えることになりました。
県では、すぐに調査委員会を設置し、原因究明と対応策を検討し、できることから早急に取り組んできました。
今回の特集では、安心して出産できる医療提供体制づくりについて、ご紹介します。 |
|
| |
平成20年5月、奈良県立医科大学附属病院を
総合周産期母子医療センターに指定しました! |
これまで緊急で、かつ高度な治療を必要とする妊婦・新生児の対応については、奈良県立医科大学附属病院、県立奈良病院が基幹病院となって関係病院とのネットワークを構築し受け入れしてきました。しかし、NICU(新生児集中治療管理室)が満床等の理由で受け入れできず、県外病院へ搬送せざるを得ないハイリスク妊婦も少なくありませんでした。
こうした状況を改善するため、奈良県立医科大学附属病院を、総合周産期母子医療センターに指定。MFICU(母体・胎児集中治療管理室)やNICUを整備しました。また、MFICUやNICUを退出した母体や新生児の治療を行う後方病床も整備。これらの整備によって、MFICUやNICUを効率的に運営することができ、新たな救急妊婦を受け入れやすくします。
さらに、県立奈良病院でもNICUの後方病床の整備を進めており、ハイリスク妊婦・新生児の受入体制の充実を図っています。 |
|
| |
|
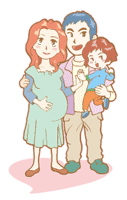 |
 |
| |
新たに整備した総合周産期母子医療センター。 |
|
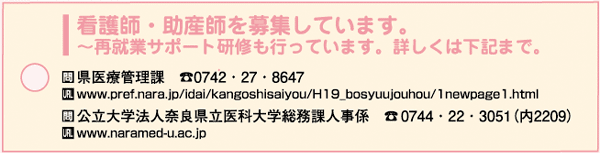 |
| |
| 産婦人科一次救急患者の受入体制が充実しました! |
休日夜間の産婦人科の救急患者については、原則として「かかりつけ医」が対応することになりますが、帰省中の妊婦などかかりつけ医が対応できない場合もあります。
こうした場合に備え、平成20年2月から開業医の協力を得て、在宅当番医制を実施し、従来から実施していた病院群輪番制と併せて、全ての休日・夜間に産婦人科一次救急患者の診療ができる体制を確保しています。
なお、4月からは協力医療機関が増え、北和地域・中南和地域それぞれに診療できる医療機関を確保できる日も増えました。 |
|
| |
 |
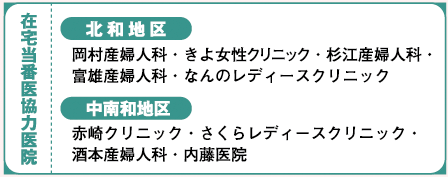 |
|
| |
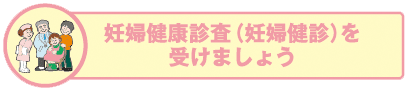 |
妊婦健康診査は、母体と産まれてくる赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかを診るための大変重要な健診です。健診を受けないまま妊娠期を過ごすと、異常に気づかず、未熟児が生まれる確率が高いうえ、場合によっては、子宮内で胎児が死亡することもあります。また、子宮外妊娠など母体の生死に関わる大きなリスクを伴うことがあります。
新しい命の誕生を家族全員が笑顔で迎えられるよう、かかりつけ医師・助産師を持ち、定期的に健診を受けましょう!
市町村では健診費用の公費負担制度があります。また、市町村民税非課税世帯の方には妊娠判定費用の補助もあります。
詳しくは、お住まいの市町村窓口にお尋ねください。 |
 |
県健康増進課 |
 |
0742・27・8661 |
|
|
| |
昨年の妊婦救急搬送事案調査委員会では、「だれが悪かったのか」ではなく「何がおかしかったのか」を検証し、今後「誰が、何をすべきか」を明確にし、できることから早急に取り組んできました。
今後も、より安心・安全に出産できる環境を提供できるよう、県としてできることに精一杯取り組んでいきます。
なお、こうした周産期医療対策を含め、救急医療体制の確保、県内の医師・看護師等の確保、医療と介護・福祉の連携などの地域医療提供体制について山積する課題に取り組むため、5月14日に奈良県地域医療等対策協議会を立ち上げました。
この協議会においても「誰が、何をすべきか」を明確にし、今年度中に具体的な対応策を明らかにしていきたいと考えています。 |
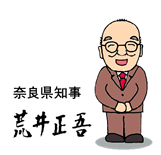 |
|