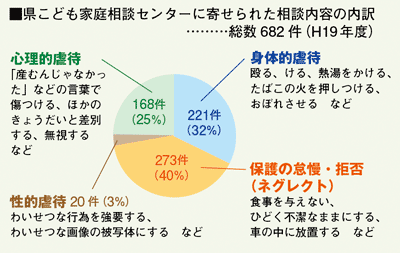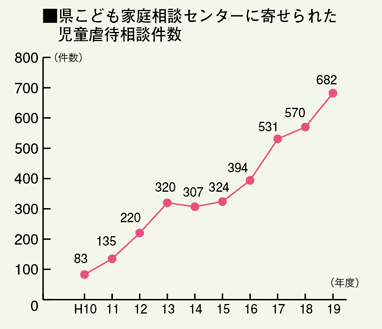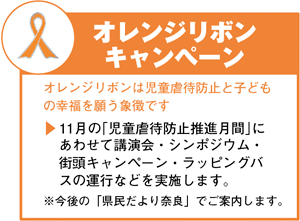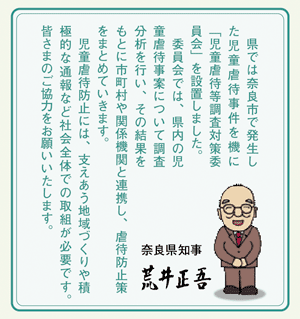|
 |
本県の児童虐待の相談件数は年々増加しています。
近隣との付き合いが薄らいでいく中で、子育ての悩みを相談できず、ひとりで悩んでいる親が増えています。さらに様々な要因が重なって不幸にも虐待に陥っている場合もあります。
すべての子どもたちの笑顔が守られるよう、皆さまの、児童虐待防止に関するご理解・ご協力をお願いします。 |
|
| |
| 児童虐待とは |
| 児童虐待は、子どものすこやかな心身の成長を阻害し、時には生命さえも奪ってしまう重大な人権侵害です。保護者が「しつけ」と、自らの行為を正当化しても、その育て方が子どもを傷つけ、痛みを与えるなど、つらく悲しい思いをさせてしまえば、それは虐待であるという視点が大切です。「しつけ」は子ども自らが判断・決定して、感情や行動をコントロールする力を育てること。それに対して、虐待は大人が力によって子どもを抑えつけ、服従を強いることであり、大きな違いがあります。 |
|
| |
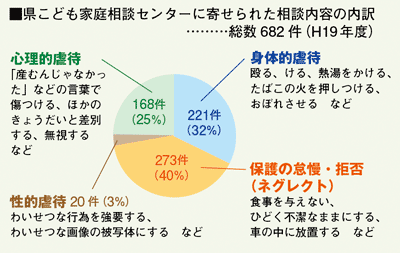 |
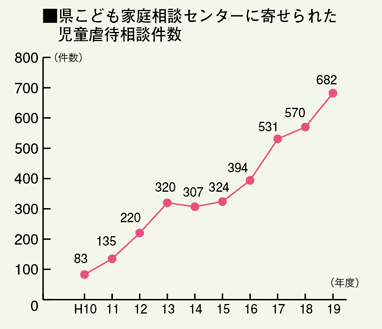 |
| |
| 虐待の早期発見 |
| 子どもへの虐待は、家庭という密室で行われるため、早期に発見することが困難です。しかし、虐待の発見につながるいくつかのポイントがあります。例えば、「子どもがぼんやりしていることが多い」「言動が乱暴で落ち着きがない」などです。地域で暮らす大人たちが、子どもに関心をもち、あたたかく見守ることが児童虐待防止の第一歩です。子どもの様子が「変だな」「いつもと違うな」と感じたら、SOSのサインととらえ、しっかりと受けとめてあげてください。 |
|
| |
| ◆ 虐待の通報から援助へ |
| 子どもへの虐待が確証できなくても、虐待を疑った段階で市町村や県こども家庭相談センターに通報することが求められています。結果として間違いであっても責任は問われませんし、誰が通報したかなどの秘密は守られます。早期の通報が、深刻な事態に陥ることを防ぎ、孤立した保護者と子どもへの支援につながります。市町村や県こども家庭相談センターでは、子どもの安全を守るとともに、関係機関と連携して子育て支援を実施しています。 |
|
| |
|
| |
| ◆ 地域社会全体での見守りを |
| 児童虐待防止にとって何よりも大切なことは、地域社会全体が子どもの成長・発達のよろこびをわかち合い、子育て家庭を応援することです。周囲に目を向け、耳をすまし、支えあう地域づくりを目指しましょう。県では地域の子育て力を充実させるための施策を展開しています。 |
|
| |
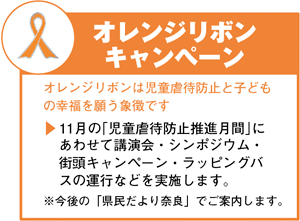 |
| |
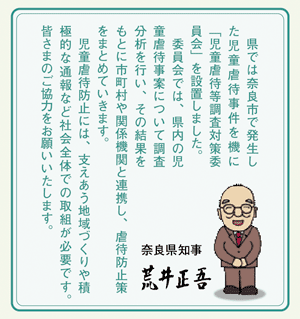 |