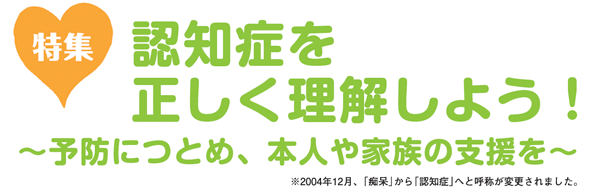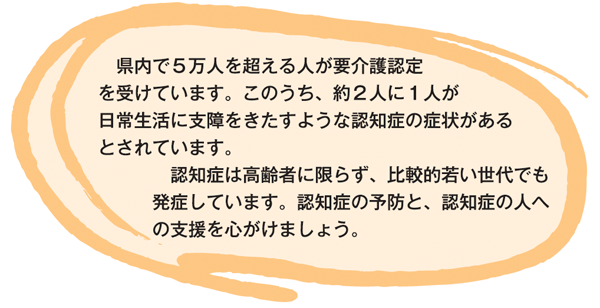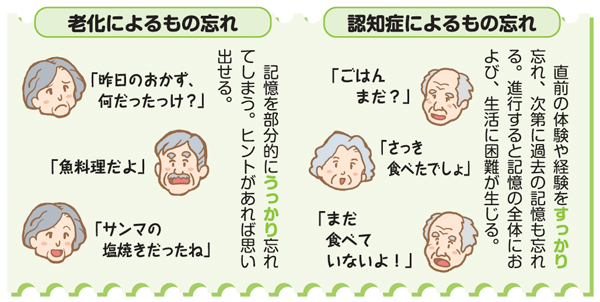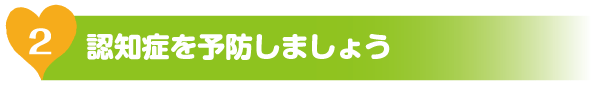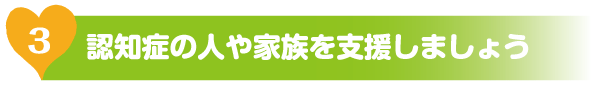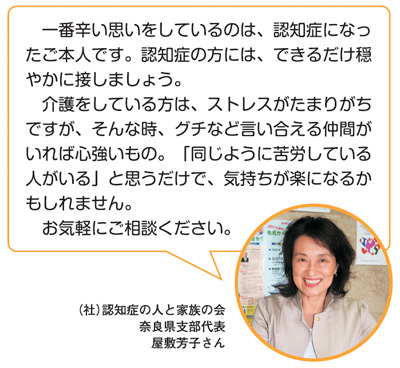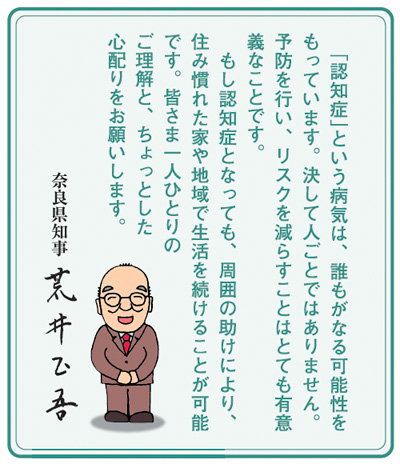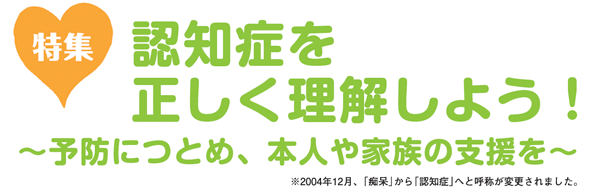 |
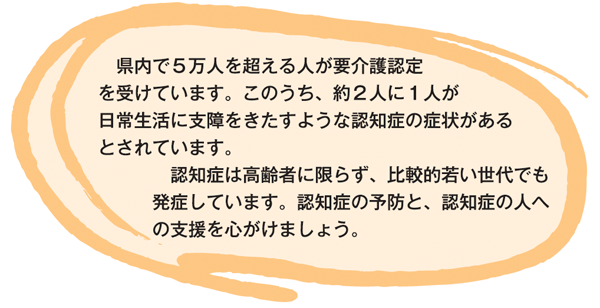 |
 |
| ◆認知症は「病気」です |
| 症状は老化による「もの忘れ」とよく似ていますが、記憶障害により日常生活に支障をきたす状態のことをいいます。 |
|
 |
| ◆早期発見・早期治療をしましょう |
- 投薬などの治療によって、症状を軽くしたり、進行を遅らせたりすることができる場合もあります。
- 疑わしい時はかかりつけ医に相談しましょう。
- 認知症の症状があっても、「認知症」ではないこともあります。
- 症状が重くなったときの介護や財産処分について、後見人を決めておく(任意後見制度)など、前もって自分の意志を示しておくことができます。
|
|
 |
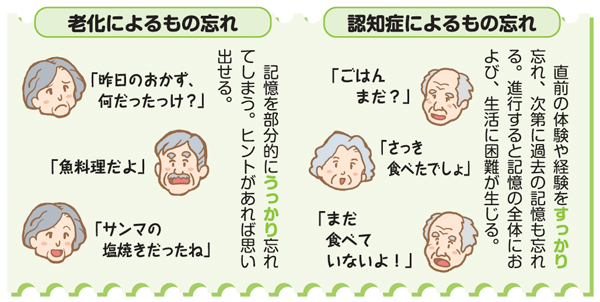 |
 |
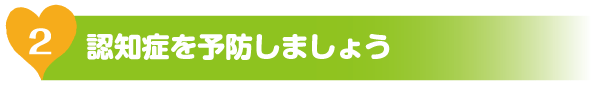 |
|
家族・友人との交流
バランスの良い食事
楽しく運動 |
 |
|
|
| 楽しく趣味活動 |
| 編み物、旅行、パソコン、料理、音読(声に出して読む)、計算など。 |
|
生活に変化を!
いつもと違う料理を作る、違う道を散歩するなど。
考えをまとめて表現しよう!
手紙や感想文を書くなど。 |
|
|
 |
| 十分な睡眠 |
|
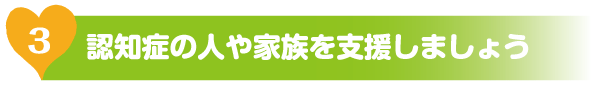 |
認知症によって、まわりの人との関係が損なわれたり、介護する家族が疲れ切って共倒れしたりというケースもあります。
しかし、たとえ認知症になっても、周囲の人の理解と気遣いがあれば、より穏やかに暮らすことができます。認知症の人や家族を見守り応援しましょう。 |
|
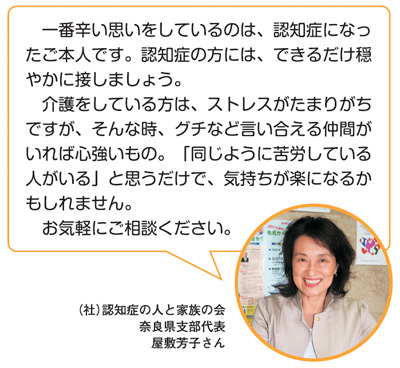 |
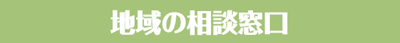 |
 |
お住まいの市町村の高齢者福祉担当課 |
 |
お住まいの市町村の地域包括支援センター |
| |
高齢者が地域で生活を続けられるよう、総合的に支援。各市町村に1ヶ所以上あります。 |
 |
(社)認知症の人と家族の会 奈良県支部 |
| |
 |
0742・41・1026(火・金10時〜15時) |
|
 |
(社)認知症の人と家族の会 |
| |
 |
0120・294・456(月〜金10時〜15時) |
|
|
|
|
 |
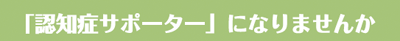 |
| 認知症について学び、自分のできる範囲で活動する「認知症サポーター」。現在、県内で約6,000人がサポーターに。「認知症サポーター養成講座」を受けて認知症への理解を深めませんか。 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
- 今までできたことができなくなる苦しみがあります
- 周囲の人の非難などに、傷つきます
- 不可解に見える行動にも、その人なりの理由があるものです
|
|
 |
|
|
 |
 |
- 穏やかな口調ではっきりと話す
- 指示はなるべく簡潔に1つだけ
- 理屈での討論はさける
|
 |
|
|
 |
|
|
|
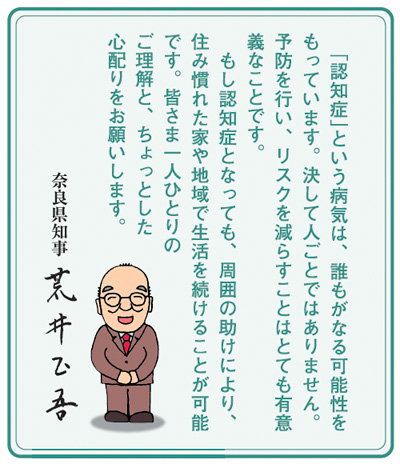 |