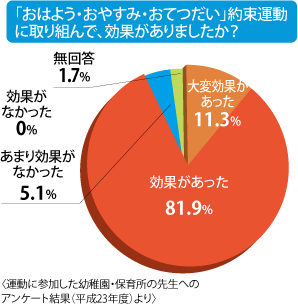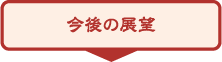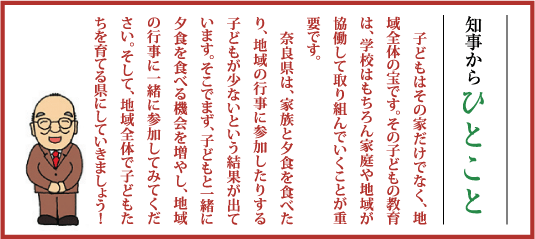皆さんは自分の子どもや地域の子どもたちに対して、どういう子であって欲しいと思いますか?
この特集では、県の子どもたちの現状や県の取り組み、皆さんにお願いしたいことなどをお知らせします。
※協働とは、目標を共有し、ともに力を合わせて活動することをいいます。 |
 |
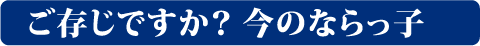 |
 |
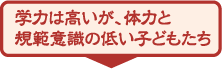 |
 |
 |
 |
学力 |
文部科学省の平成22年度全国調査によれば、小学生の国語と算数の学力は全国12位、中学生の国語と数学の学力は全国18位となっており、学力については相対的に高いといえます。
 |
 |
体力 |
しかし、体力・運動能力については、小学生が全国46位、中学生が全国43位と低い状況です。
 |
 |
規範意識 |
学校の規則を守る子どもの割合については、小学生が全国45位、中学生が全国46位となっています。また、小・中・高等学校の児童生徒1000人当たりの暴力行為の発生件数は、全国平均が4.4件であるのに対し、平成21年度より減少したものの、県は7.6件で全国ワースト7位であるなど、規範意識が低いことが分かります。 |
 |
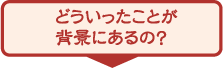 |
 |
| 体力や規範意識が低いことについては、さまざまな背景が考えられます。 |
 |
 |
子どもたちの遊びの変化 |
社会の変化とともに、子どもたちの遊びが変わってきました。奈良県では、3時間以上テレビゲームをする子どもの割合が、小学生は全国11位、中学生は全国5位と高く、外遊びをする時間が少ないことがうかがえます。
 |
 |
遊ぶ時間のない子どもたち |
塾に通っている子どもの割合は、小学生が約56%で全国3位(全国平均は約47%)、中学生が約74%で全国2位(全国平均は約63%)となっており、遊ぶ時間がなかなかとれない子どもたちの実態が分かります。
 |
 |
定着していない基本的な生活習慣 |
寝るのが午後11時より遅い子どもの割合は、下のグラフのように、小学生が全国2位、中学生が全国1位、朝食を毎日食べている子どもの割合は、小学生が全国45位、中学生が全国43位となっており、基本的な生活習慣が定着していない子どもたちが多いことが分かります。 |
 |
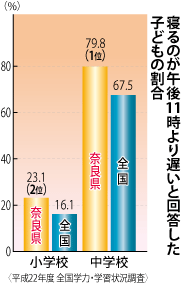 |
 |
 |
 |
家庭や地域と関わる時間が少ない子どもたち |
平日、家の人と一緒に夕食を食べている子どもの割合は、下のグラフのように、小中学生とも全国46位となっています。
また、地域の行事に参加している子どもの割合は、小学生が約56%で全国38位(全国平均は約62%)、中学生が約28%で全国43位(全国平均は約34%)となっています。
子どもたちが家庭や地域と関わる時間がなかなか持てていないことがうかがえます。 |
 |
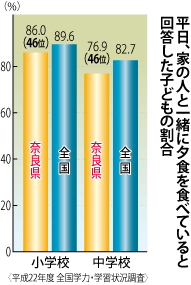 |
 |
| これらの背景から、学校だけでなく家庭や地域による教育力が十分に発揮できていないのではないかということが考えられます。 |
 |
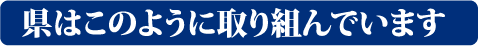 |
 |
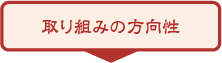 |
 |
 |
 |
体力が低いことについて |
まず、子どもたちが外で遊ぶ機会を多くするために、遊び場の環境を変えるという取り組みが考えられます。
また、生活習慣と運動能力の関係についてみると、規則正しい生活ができている子どもの方が運動能力が高いということがいえます(下グラフ)。そこで、運動能力を高めるためにも、子どもたちに規則正しい生活リズムが身に付くことは重要だと考えられます。 |
 |
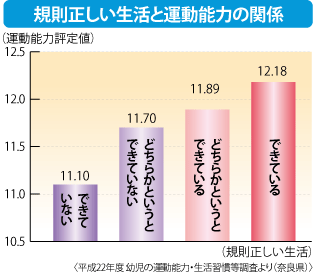 |
 |
 |
 |
規範意識が低いことについて |
まず、子どもの教育の基本である「家庭」で行える、規範意識を育む取り組みが考えられます。
また、家庭や地域とのつながりを深め、地域のみんなで子どもを育てるために、家庭と地域と学校が協働して、子どもの教育に取り組むことが考えられます。 |
 |
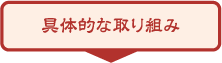 |
 |
 |
 |
遊び場の環境を変える取り組み |
|
 |
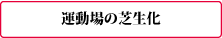
子どもたちが外で遊びたくなるように、平成21年度より小学校の運動場を芝生化することを進めています。芝生だとけがが少なく、気持ちよく運動できるので、外遊びをする子どもたちが多くなり、体力の向上につながります。現在、県内15校の小学校で運動場の芝生化が行われ、体力テストの多くの種目で記録が県平均より伸びています。 |
 |
 休み時間のようす 休み時間のようす |
 |
 |
 |
基本的な生活習慣の定着や家庭での会話の促進に向けた取り組み |
|
 |
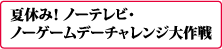
子どもたちの基本的な生活習慣の定着とともに、家庭での会話の促進を目指して、県内全ての小学3年生とその保護者を対象に、今年度から始めた取り組み。夏休み期間中、毎週2日間、テレビを見ない・ゲームをしない日を決めて、達成できたらシールを貼ります。実施後、保護者の方からは「宿題もお手伝いも自分から進んでするようになりました」「いつもよりたくさんお話ができて楽しかったです」といった声が寄せられました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
家庭で規範意識を育む取り組み |
|
 |
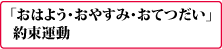
幼児期における子どもの基本的な生活習慣の向上や、規範意識の育成を目的にした取り組み。県内の幼稚園・保育所の3〜5歳の子どもたちを対象に、2年前から実施しています。7〜8月の2か月間、子どもたちは「おはようを言う」「おやすみを言う」「おてつだいをする」という3つの約束が守れたらカレンダーに色を塗ったりシールを貼ったりします。
楽しみながら運動に取り組んだ結果、あいさつやお手伝いをする子どもが増え、9割を超える保護者や先生から、大切で効果があると高い評価を得ています。 |
 |
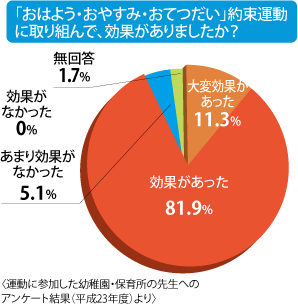 |
 |
 |
 |
家庭と地域と学校が連携した取り組み |
|
 |
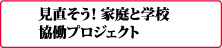
家庭と地域と学校が同じ目標に向かって子どもたちを育てられるように、昨年度から始めた取り組み。県内の5つの小学校をモデル校として、地域と協働したあいさつ運動や、地域行事への参加の呼びかけなどに取り組んでいます。モデル校の一つである奈良市立飛鳥小学校で、地域の代表として活動されている、飛鳥地区自治連合会会長の大西昇(のぼる)さんにお話をうかがいました。
「この活動を始めていくうちに、『子どもたちがあいさつをきちんとしたり、家に帰ってから学校であったことなどを話したりするようになった』と話される親御さんが増えました。子どもは家庭と地域と学校の中で日々育っています。地域の行事などに参加されたことのない親御さんは、ぜひ一度、お子さんと参加してみてください」 |
 |
 |
 |
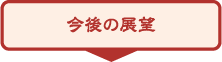 |
 |
この他、今年度より3つのフェスタを開催しました。学習意欲の向上を目指した「わくわくまなびフェスタ」と、規範意識の向上を目指した「ふれあいフェスタ」、体力の向上を目指した「チャレンジ運動フェスタ」です。
また、「奈良県地域教育力サミット」を初めて開催しました。荒井知事をはじめ、行政・経済界の代表者や公私の教育関係者が一堂に会し、家庭と地域と学校が連携して地域の教育力を向上させるため、意見交換しました。
今後も、県の子どもたちに見られる課題が解決されることを目指して、家庭と地域と学校が協働して子どもたちを育てられるように、さまざまな取り組みを進めていきます。 |
 |
 |
| 平成23年度 奈良県地域教育力サミット |
|
 |
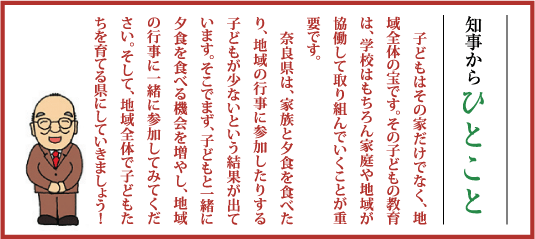 |
 |
 |
県教育委員会事務局企画管理室 |
 |
0742-27-9830 |
 |
0742-27-2985 |
|
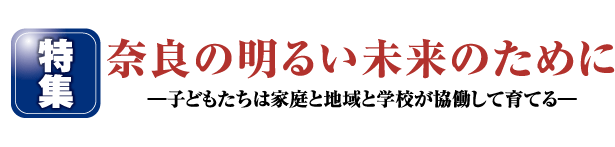
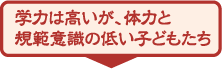
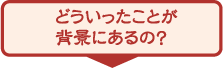
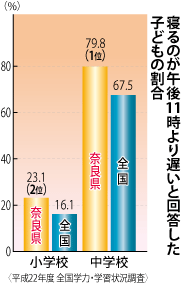
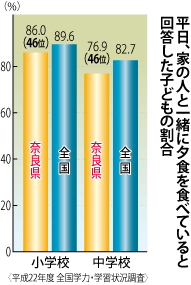
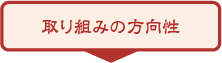
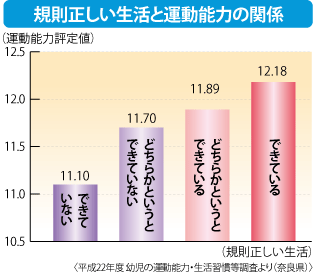
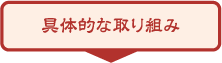
 休み時間のようす
休み時間のようす