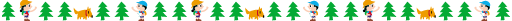所得区分の判定
所得区分の判定
所得額に応じて、現役並み所得者、一般・低所得者に区分され、医療機関の窓口で支払う
自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
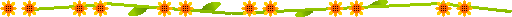
 現役並み所得者
現役並み所得者
その世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の所得または収入で判定します。(自己負担割合:3割)
| (1) |
課税所得額が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者 |
| (2) |
課税所得額が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者 |
※ただし、収入額が下記A~Cの一定基準を満たす場合は、市町村に申請することで1割負担になります。
| A |
世帯内に他の後期高齢者医療の被保険者がいない場合 |
収入額が383万円未満であれば、申請によって1割負担になります。 |
| B |
世帯内に他の後期高齢者医療の被保険者がいる場合 |
収入の合計額が520万円未満の場合、申請によって1割負担になります。 |
| C |
世帯内に他の後期高齢者医療の被保険者がおらず、70~74歳の者がいる場合 |
被保険者だけの収入が383万円以上で、現役並み所得者になるが、同一の世帯にいる70~74歳のものを含めた収入が520万円未満であれば、申請によって1割負担になります。 |
 一般II:2割
一般II:2割
下記の(1)、(2)の両方に該当する場合
| (1) |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。 |
| (2) |
同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者が1人の場合は200万円以上
被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上
|
 一般I:1割
一般I:1割
現役並み所得者・一般II・低所得I・低所得II のどれにも該当しない方
 低所得II:1割
低所得II:1割
その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である後期高齢者医療被保険者
 低所得I:1割
低所得I:1割
その属する世帯の世帯主および世帯員全員が非課税かつ基準額以下の所得である後期高齢者医療被保険者