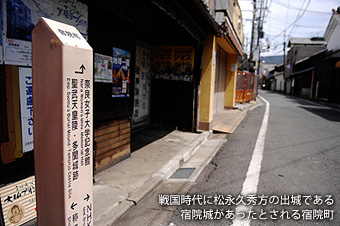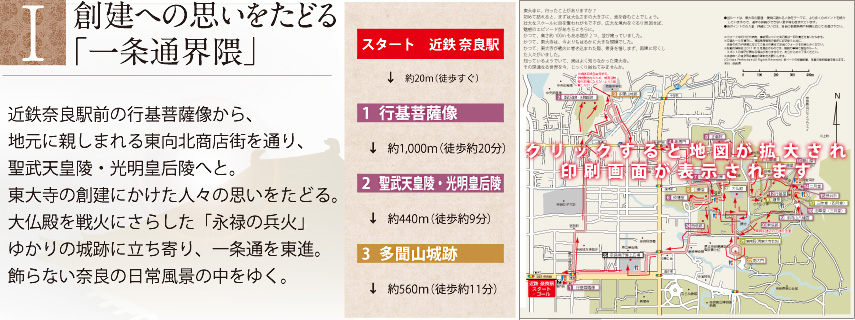
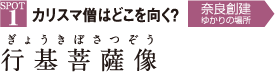
「ぎょうきさん」の愛称で親しまれる高僧、行基。近鉄奈良駅前の噴水広場に立つ行基菩薩像は、奈良県民にとってお馴染みの待ち合わせ場所だ。
行基は奈良時代、民衆から絶大なる信頼を得ていた。743年、聖武天皇により「大仏(正式には盧舎那仏)造立の詔」が発せられると、寄進を推進する役目「勧進」に起用される。行基は弟子を率いて全国各地を東奔西走。民衆の心をまとめ上げ、大仏造立に大きな役割を果たした。しかし752年、大仏開眼供養会が執り行われるが、その場に行基の姿は見当たらない。大仏完成を待たずして、その3年前、82歳でこの世を去っていたからだ。
ところで、この行基菩薩像の向きにお気づきだろうか?目を閉じ、合掌するその先にあるのは、ほかならぬ東大寺の大仏さまである。
- 奈良市東向中町
- 見学自由
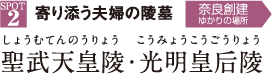
東向北商店街を通り、レトロな外観をした奈良女子大学の正門前を横切る。北上し、一条通り(県道104号)に突き当たれば、聖武天皇陵と光明皇后陵はすぐそこだ。陵墓を前に、まずは大仏造立を発願するに至った聖武天皇の心情に思いを馳せてみたい。
727年、聖武天皇と藤原光明子(後の光明皇后)との間に基親王(もといしんのう)が生まれる。念願の皇太子だ。しかし翌年、基親王は1歳に満たずに亡くなってしまう。729年には長屋王の変が起こり、737年には天然痘が流行。当時権勢を振っていた藤原四兄弟をはじめ多くの人々が病死する。わが子を亡くした悲しみに加え、相次ぐ政争や疫病の流行。聖武天皇は苦悩する。この閉塞的な政情不安を打破するにはどうすればいいのか…。
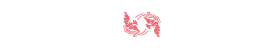
聖武天皇は740年2月、河内国智識寺で盧舎那仏を拝した。盧舎那仏は『華厳経』の教主だ。華厳の教えとは、世界のあらゆる要素はすべて網目のように何らかのつながりを持ち、互いに生かし生かされているというもの。「このような世界観を説く華厳の教えを広めれば、人民が本当に幸せなれる」。華厳の教えに共感した聖武天皇は、その象徴である大仏の造立を決意する。
聖武天皇と、その妻である光明皇后は、仏教に深い知識と篤い信仰心を持ち続けた。奈良時代の華やかな天平文化は、まさにこの二人が育んだといっても過言ではない。聖武天皇陵の東側には光明皇后陵が寄り添うようにしてたたずみ、2つの陵墓は1本の道でつながっている。
- 奈良市法蓮町
- 拝観自由
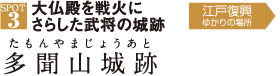
閑静な住宅地の路地裏を抜ける。北に向かって伸びる緩やかな坂道の先に、奈良市立若草中学校の校門が見えてくる。校舎へと続く石階段の脇に「多聞城跡」の石碑が立つ。多聞山城(多聞城)は、わが国で初めて天守閣や多聞櫓を考案・構築した城ともいわれる。かつて城内には御殿など豪華な建物が並び、その美しさは宣教師ルイス・フロイスによってヨーロッパにも伝えられた。
応仁・文明の乱後、室町幕府は影響力を失った。各地で下克上が繰り広げられ、時はまさに戦国時代。松永久秀は1560年、大和国の支配拠点として、眉間寺山(みけんじやま。現在は多聞山とも呼ばれる)に多聞山城を築いた。久秀は主君の三好長慶が病死すると自らの勢力を拡大しようとするが、同じ三好氏の重臣である三好三人衆らと対立。三人衆は筒井順慶ら大和国衆と結束し、久秀を攻めにかかる。
1567年(永禄10年)5月、ついに両者は東大寺にて衝突、戒壇院が炎上する。10月には、大仏殿に陣を張る三好勢と久秀が激突、大仏殿が炎上する。僧らは必死の消火活動を行うが、大仏の頭部や腕は落ち、上半身は熱で溶け落ちてしまう。この三好・松永が起こした乱「永禄の兵火」によって、東大寺の多くの伽藍が焼失することとなった。
その後、多くの人々の献身的な協力によって、東大寺は不死鳥のごとく復興を遂げるが、その中には織田信長や徳川家康らの名前もあった。武将たちにとっても、東大寺は特別な寺院だったのだ。
若草中学校の正門を入ってすぐ右側には、石仏や石塔を集め供養されている一画がある。これらは、かつて多聞城築城の折に、土塁の基礎として大量に地中に埋められた石仏・石塔類たちで、学校の敷地から掘り出されたものだ。若草中学校では毎月15日、教職員たちによる供養を行っている。また、9月にはPTAの協力を得て草刈りを行い、公慶上人の墓所でも知られる五劫院(奈良市北御門町)の住職に法要を営んでもらっているのだとか。
多聞山城跡に建ち、その豊かな歴史を地域ぐるみで守り継ぐ中学校―。その貴重な環境で学んだことは、卒業した後も、生徒一人ひとりの誇りとなるに違いない。
- 奈良市法蓮町1416-1
(奈良市立若草中学校敷地内) - 開校時間中、多聞山城跡石碑自由見学可
※学校敷地内のため、教育活動等の支障にならないようご留意ください。
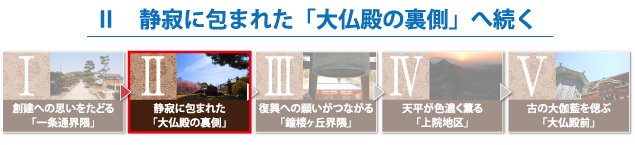
| 710 | 平城遷都 | ||
| 724 | 聖武天皇即位 | ||
| 728 | 基親王が死去 | ||
| 729 | 長屋王の変 | ||
| 741 | 国分寺、国分尼寺建立の詔 | ||
| 743 | 「盧舎那大仏造立の詔」 | ||
| 752 | 大仏開眼供養会 | ||
| 実忠により修二会が創始 | |||
| 754 | 鑑真の授戒 | ||
| 756 | 聖武上皇、崩御 | ||
| 794 | 平安遷都 | ||
| 1180 | 治承の兵火 | ||
| 1181 | 重源、大仏殿の再興を計る | ||
| 1185 | 源頼朝、再興を助成 | ||
| 大仏開眼供養会 | |||
| 1192 | 源頼朝が鎌倉幕府を開く | ||
| 1195 | 大仏殿落慶供養 | ||
| 1206 | 重源、入寂 | ||
| 1338 | 足利尊氏が室町幕府を開く | ||
| 1467 | 応仁の乱 | ||
| 1567 | 永禄の兵火 | ||
| 1573 | 織田信長が室町幕府を滅ばす | ||
| 1590 | 豊臣秀吉が天下を統一 | ||
| 1600 | 関ヶ原の戦い | ||
| 1603 | 徳川家康が江戸幕府を開く | ||
| 1684 | 公慶、大仏殿再建事業開始 | ||
| 1692 | 大仏の修復が完成 | ||
| 開眼供養を営む | |||
| 1705 | 公慶、入寂 | ||
| 1709 | 大仏殿落慶供養 | ||
| 1868 | 明治維新 | ||
| 廃藩置県が行われ奈良県が成立 | |||
| 神仏判然令が出される | |||
| 1884 | 正倉院が宮内庁管轄となる | ||
| 1903 | 大仏殿、修復開始 | ||
| 1915 | 大仏殿落慶法要 | ||
| 1952 | 大仏開眼1200年法要 | ||
| 1980 | 大仏殿、昭和大修理完了 | ||
| 1998 | ユネスコ世界遺産に登録 | ||
| 2002 | 大仏開眼1250年法要 | ||
| 2010 | 平城遷都1300年祭 | ||