宅地建物取引業と人権-共生社会の実現をめざして-
|
奈良県では、県民一人ひとりの人権が真に尊重される自由で平等な社会を築くため、平成16(2004)年3月「奈良県人権施策に関する基本計画」を策定し、また平成9(1997)年3月に「奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例」、平成31(2019)年3月には「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」を公布・施行しています。
近年、急速に国際化、高齢化が進み、わたしたちの身近でも外国人や一人暮らしの高齢者が増えています。
もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居をことわられたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。
常に相手の立場になって考えましょう。
さまざまな人々との出会いを通して、私たちは新たな発見をしたり、自分の生活を豊かにすることができます。
一人ひとりの人権を大切にする、住みよい街にしていきましょう。
|
宅地建物取引での人権問題に関わる対応について、次に例をあげますので、参考にしていただくとともに、
皆様で話し合ってください。(なお、お客様とのやりとりの際には、一方的な啓発ではなく、対話がとぎれたり
することのないように、相手の理解をうながすような話し方を心がけましょう)
ケーススタディ1
●「この地区は同和地区か?」「校区内に同和地区があるか?」などと、尋ねられたら…
●「ここは同和地区だから契約の申込みを断りたい(または契約を解除したい)」と言われたら…
●「なぜこの地区が同和地区(または校区)であるとを教えてくれなかったのか」と苦情があった…
- 同和地区かどうか、なぜ気にされるのですか。
- そのような意識が同和問題の解決を遅らせることになり、多くの人たちを傷つけ、苦しめていることを考えてみてください。
- 同和地区かどうかを調査したり、教えたり、それを理由に契約解除したりすることは、差別行為にあたります。また、同和地区かどうかについては、宅地建物取引業法上も、答える義務はありません。
- これまでの教育・啓発の取組で、人々の人権意識は大きく変わってきています。お客様にも、間違った先入観や偏見にとらわれないで、この問題を正しく理解していただきたいと考えています。
ケーススタディ2
●「この物件は、同和地区にあるから安いのか?」と、尋ねられたら…
- 建物の値段は、おもにその土地の価格や建設費などかかったコストで決まり、土地の価格は、公示価格や交通の便など様々な要因で決まります。
- 購入価格は、ご自身が妥当と思われ納得されることが大切だと思います。
- 「同和地区にあるから安いのでは?」と思われたのは、どうしてですか。
- それは、同和地区に対する差別意識の表れではありませんか。
- これまでの教育・啓発の取組で、人々の人権意識は大きく変わってきています。お客様にも、間違った先入観や偏見にとらわれないで、この問題を正しく理解していただきたいと考えています。
ケーススタディ3
●「外国人や障害者であることを理由に入居を断りたい」と言われたら…
- 「入居申込者が外国人や障がい者である」という理由だけで入居を断ることは、差別です。予断や偏見に基づく差別がいかに人の心を傷つけるか、よく考えてください。
- 幸せに暮らすことは、私たちみんなの願いです。お互いの「居住・移転の自由」は尊重しなければなりません。
- あなたやあなたのご家族が、このような差別を受けたらどのように思われますか?
|
同和問題に関する差別意識を助長する広告とは?
「同和問題に関する差別意識を助長する広告」とはどのようなものでしょうか。
これまでの例では、キャッチワードとして「やっと出ました○○校区!」、「○○の学校です!」、「○○校区」、「○○校近く」、「校区よし」等の同和地区を含まない小・中学校の校区を表示した広告、あるいは、一枚のチラシにたくさんの物件を紹介して同和地区を含まない校区の物件についてだけ校区の表示をしたものがありました。
ご存知のように、不動産の表示に関する公正競争規約では、生活関連施設として学校を表示する場合は現に利用できるもので、物件までの道路距離を明らかにし、その名称を表示することになっています。
校区をキャッチワードにした理由は何なのでしょう。
特定の物件だけに校区を入れた意図は何なのでしょう。
このように表示された校区に同和地区が含まれないのは何故でしょう。
同和地区を含まない校区を特別に扱った広告は、広告者の意図がどのようなものであっても、部落差別につながるものであり、部落差別意識を助長することになります。
広告は、宅建業法や公正競争規約に違反していないかをチェックするとともに、人権尊重の立場から、差別にかかわる表示がないかもチェックし、正しい広告を行ってください。
2.入居差別をなくすために
現在、不動産については、「所有から利用へ」といわれるように、賃貸借がますます注目されています。しかし、居住用住宅賃貸借(借家)契約においては、
・契約締結時の申込金(預り金)
・更新のあっせんに伴う手数料(更新料)
・明渡し時の敷金の精算
をめぐるいわゆる「3大トラブル」をはじめ多種多様な紛争が発生しています。
一方、賃貸住宅の取引に際しては、外国人や障がい者、高齢者、女性の人権など様々な人権問題が発生する可能性があります。
すべての人の人権が尊重される“まち”をわたしたちみんなの力で築くよう次のケースを参考に考えてみましょう。
外国籍の彼は、仕事の都合でアパートを探しています。
ある日、頼んでいた不動産業者から電話がありました。
「いい物件が出ました。家主さんも来ていますので、今から一緒に部屋を見に行きませんか。」
彼は期待と不安を持ちながらすぐ出かけました。
事務所で愛想よく出迎えた家主は、彼が外国人と分かったとたん態度を変え、言いにくそうに言ったのです。
「あの部屋は先ほど決まりました。」
国籍や生活習慣が違うということを、気にする風潮があるのではないでしょうか。お互いに違いを認め、理解し合えるようにしたいものです。
ケーススタディ
☆家主から宅建業者への相談
以前に外国人、父子・母子家庭の人にアパートを貸したらトラブルがあったから、生活習慣や文化が違う人に貸したくないのですが何か良い方法はないですか…?
☆某外国人(借主)の意見
夫が外国人ということで入居を断られました。最初は「外国人にはハンコがないから」などと、口ごもってましたが、「ハンコはある」と言うと、とうとう「外国人なので」と本音を言いました。日本人でないという理由だけで断ることにショックを受けました。
☆某女性(借主)の意見
申込み時に母子家庭であるということを言ったら、「過去に母子家庭にかかるトラブルが多く、たとえば子どもを一人で部屋において仕事に出るとか、収入面でも不安があるので…」と断られました。納得がいきません。
このようなことを理由にして、入居を断るのは差別です。過去にトラブルがあったとか、他から聞いたとかいうことで、入居を断るのは、正しいことではありません。また、生活習慣や文化の違いも理解しあうようにしましょう。
人権に配慮した賃貸住宅の仲介業務
賃貸住宅の入居に関して、外国人であるから、あるいは高齢者、障がい者等であることを理由として契約の履行に直接関係のない事柄で入居を拒否するのは、差別につながります。
このような入居差別は家主だけの問題でしょうか、仲介を行う宅地建物取引業者の皆さんの業務の中に差別を助長するものはないでしょうか、また、逆に入居差別をなくす手掛かりはないでしょうか。
(1)入居申込書の本籍・国籍欄の廃止
今だに、入居申込書に本籍・国籍を記入するよう求めてはおられませんか。
本籍・国籍は入居とは関係がありません。本籍から同和地区出身者かどうかを調査することや、外国人であることを理由に入居を断ることは重大な人権侵害です。
本籍・国籍の記入を求めることは、差別につながる行為ですのでやめましょう。
(2)家主への啓発
|
仲介業務を行う宅地建物取引業者の皆さんが、自己の業務を点検し、人権に配慮した書式等に変えるだけでは入居差別はなくなりません。
入居申込者に対して、外国人や高齢者、障がい者等であることなど本人の責任ではないことを理由として入居を拒否することは差別につながります。このことを家主に啓発できるのは、家主から信頼され、仲介の依頼を受けている宅地建物取引業者の皆さんです。
宅地建物取引業に従事する皆さんに今最も求められていることは、常に高い人権意識を持ち、信義を旨とし、誠実に業務を行うとともに、家主に対して、差別につながる行為については改めるよう働きかけることです。
仲介の依頼を受ける場合には、入居条件や提出書類について差別につながるものがないかについて充分に注意を払うとともに、今まで何気なく求めているものであっても、それが差別につながるものであれば、家主に説明して働きかけながら改善を図ってください。
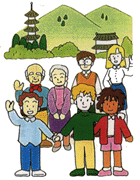
|
|
※上記の内容をPDFファイルにまとめました。社員研修などで印刷・配布するなど、ご活用ください。
(ダウンロードは下記をクリック)
『宅地建物取引業と人権』(PDF形式)
|
あらゆる差別の撤廃にむけた不動産業界としての申し合わせ
今日、私たちの社会では「日本国憲法第14条(法の下の平等)」や「奈良県あらゆる差別の撤廃及び人権の尊重に関する条例(1997年3月)」の趣旨に則り、社会的身分や人種、国籍、性別、障がいの有無等による差別をなくす不断の努力が続けられています。
不動産取引に関わる私たちも、企業・事業者の社会的責任を自覚し、業務に際して人権を尊重し、人権侵害をすることのないよう、以下の事項に努めます。
1.人権に関する啓発・研修を行い、人権意識の高揚に努める。
2.国籍、障がい、高齢等の理由により入居機会を制約し、これを助長する差別的行為をしな
い。また、その関係する家主等に対して、人権問題についての理解を求めるよう努める。
3.差別につながる不適切な広告や表示をしない。
4.物件に関し、同和地区であるかないか、または同和地区を校区に含むかどうかなど、差別に
つながる問い合わせ等については、宅地建物取引業法第47条に関する国土交通大臣答弁に
基づき、調査、報告、説明、教示をしない。
(公社)奈良県宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会奈良県本部
|
※平成28(2016)年8月、県内不動産業界団体である上記公益社団法人2団体の間で上記の申し合わせが行われています。奈良県も、この申し合わせに大いに賛同しているところです。
宅建業者様におかれましては、この申し合わせを店内や事務所内で掲示いただくなど、人権啓発へのさらなる取組についてご協力をいただきますようお願い申し上げます。
申し合わせの印刷用データのダウンロードはこちら(PDF形式)