県では、昭和57年の大和川大水害をきっかけに、国、市町村、流域に住む人々や企業などの協力のもと、河川改修などの「ながす対策」、降った雨を一時的に貯める「ためる対策」、浸水の恐れのある区域の土地利用を抑制する「ひかえる対策」を3本柱とした流域治水を進めています
川西町・保田地区で
保田(ほた)遊水地が運用開始!
遊水地とは、大雨のときの洪水を一時的にためておく施設のこと。堤防の一部を低くした「越流堤(えつりゅうてい)」から洪水を遊水地へ流し込み、下流に流れる水の量を抑えることで、川の氾濫を防ぎます。
国土交通省が整備し、令和7年6月から運用が始まった川西町の保田遊水地は、面積約7ha、最大で約23万㎥の洪水をためることができます。さらにこの保田遊水地は、大和川の洪水(外水)だけでなく、周辺に降った雨による水(内水)も取り込める、全国的にも珍しい「内水・外水対応型」の遊水地です。
この施設の完成により、大和川の洪水対策に加え、周辺地域の浸水被害の軽減にも大きな効果が期待されます。

大和川の水を一時的にためて、約23万m³の洪水をカット!周辺の床上浸水を防ぎ、浸水する範囲も約15haから約9haに減少します
平常時は“にぎわいの場”として活躍!
国土交通省により整備された保田遊水地を、川西町では、災害時以外にも地域のために有効活用するため、「新たなスポーツ体験と交流の場」をコンセプトに、「オーバルパークかわにし」を整備しました。国内では初めて、国際規格に準拠したインラインスピードスケート競技用のオーバルトラックが整備され、今年4月にはプレオープンとして、世界を目指す選手たちによる第70回全日本トラックスピード選手権大会が開催されました。
そのほかにも、バスケットボールを楽しめるコートや芝生広場など町内外の人が気軽に集い、交流できるエリアもオープン予定。(現在、遊水地の一部では工事が継続しており、オープン時期については決まり次第、川西町のホームページなどでお知らせされます。)
防災とにぎわい、両方の役割を持つ保田遊水地を通じて、地域のさらなる活性化が期待されています。
雨水貯留施設の整備で
水害に強いまちへ
大雨で川の水位が上がると、雨水を川に流せなくなり、あふれた雨水で土地や建物が浸水してしまう「内水氾濫(ないすいはんらん)」が起こることがあります。これを防ぐため、降った雨を一時的にためておくのが「雨水貯留施設」です。
内水氾濫による浸水被害がたびたび発生している大和川流域の市町では、県の財政支援や技術支援のもと、雨水貯留施設の整備を進めています。
令和6年度には、新たに天理市・三郷町・王寺町で雨水貯留施設が完成!施設が完成した市町では、これまでよりも水害に強いまちへと変わっています。
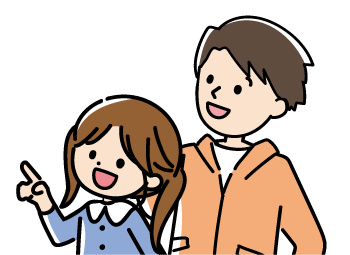
実際に貯留施設を整備した地域では、大雨でその効果を実感したという声も聞いたよ
全国初
新たな浸水被害を防ぐため
貯留機能保全区域を指定
田畑などの土地には、雨が降ったときに雨水を一時的にためておく貯留機能があります。しかし、こうした土地に盛土(もりど)がされると、水の行き場がなくなって、これまで浸水していなかった地域にまで雨水が広がり、新たな浸水被害が起こるおそれがあります。
「貯留機能保全区域」は、新たな盛土をひかえることで、その土地が本来持っている“雨水をためる力”をできるだけ守ることを目的とした制度です。
県では、令和6年度に全国で初めてこの区域を指定し、地域の皆さんと協力しながら、浸水被害の軽減に取り組んでいます。
全 国 初
●川西町 唐院(とういん)地区
(約3.7ha)
●田原本町 西代(にしんだい)地区
(約11.6ha)
全国で3例目
●大和郡山市 番条(ばんじょう)地区
(約3.6ha)
貯留機能保全区域の指定には、土地所有者の方の同意が必要で、同意を得られた箇所で指定を進めています
貯留機能保全区域に指定された区域内で、盛土などを行おうとする場合は「届出」が必要です
雨水をためておく機能のある農地のおかげで、その周辺で住居を構えて生活することができていた
農地などで盛土が行われると、逃げ場を失った雨水が周辺家屋に拡がり、浸水被害が発生する恐れが高まる
正しい情報を知り、適切な行動で身を守りましょう
河川のイマが一目でわかる
奈良県河川情報システム
観測した雨量や河川の水位、河川監視カメラの画像を、県のホームページにある「奈良県河川情報システム」でリアルタイムに公開しています。
表示された地図から見たい地域を選ぶだけで、最新の河川の状況をすぐに確認することができます。