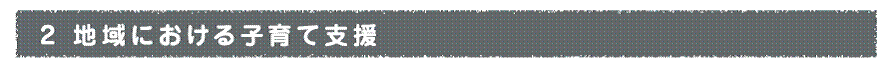
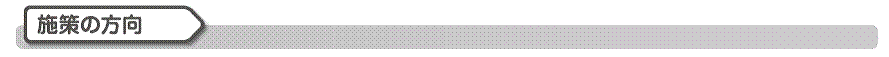
(1)地域における子育て支援の充実
子育て中の親子が身近な場所で気軽に交流し、相談できる子育て支援の拠点づくりや、地域における育児の相互援助活動の活性化を推進する市町村を支援します。また、地域で子育てに関する相談が円滑に行われるよう、相談体制を整備・充実しそれらの機関相互の連携を図るとともに、地域全体が子育てを応援する取組を推進します。
|
施策方向の目標指標
|
現状
(平成20年度)
|
目標値
(平成26年度)
|
担当課
|
|
※地域子育て支援拠点事業設置箇所数 |
ひろば型
|
22箇所
|
47箇所
|
こども家庭課
|
|
センター型 |
25箇所
|
23箇所
|
|
児童館型
|
0箇所
|
1箇所
|
|
※ファミリー・サポート・センター設置市町村数 |
7市町村
|
12市町村
|
雇用労政課
|
※は全国共通で設定する事業項目
●主な取組
子育て支援体制の拡充
・子育て中の親子が身近な場所で気軽に交流し相談できる「つどいの広場」や「地域子育て支援センター」等の子育て支援の拠点づくりや地域における育児の相互援助活動である「ファミリー・サポート・センター」等をより活性化するように市町村に働きかけるとともに、子育て中の保護者に対して、制度の周知を図ります。
・地域の子育て支援に取り組む県内の大学と連携し、子育て支援者の資質向上を図る施策を検討し実施します。
・「なら子育て応援団」をはじめとする地域社会全体が子育てを応援する取組を実施します。
相談窓口の体制の整備・充実
・市町村や地域の主任児童委員、保育所や幼稚園等の身近な相談機関と、こども家庭相談センター、児童家庭支援センター等の専門相談機関とが連携し、幅広い相談体制の整備・充実を図ります。
(2)多様な保育サービスの充実
市町村と連携し、待機児童の解消のため、保育所の整備を促進するとともに、親の就労形態の多様化等に対応した保育サービスや、子どもの急な病気に対応した保育サービス、幼稚園での預かり保育等、多様な保育の充実を図ります。
また、保育の質を向上するため人材養成を図るとともに、保育所と幼稚園の教育・保育内容の整合性の確保などを図り、就学前教育の連携、充実を図ります。
|
施策方向の目標指標 |
現状
(平成20年度) |
目標値
(平成26年度) |
担当課 |
|
※通常保育事業(認可保育所)受入可能児童数 |
3歳未満児 |
8,272人
|
8,940人
|
こども家庭課
|
|
3歳以上児 |
13,874人
|
13,837人
|
|
※特定保育事業
実施箇所数 |
7箇所
|
9箇所
|
こども家庭課
|
|
※延長保育事業
実施箇所数 |
136箇所
|
154箇所
|
こども家庭課
|
|
※夜間保育事業
実施箇所数 |
1箇所
|
3箇所
|
こども家庭課
|
|
※休日保育事業
実施箇所数 |
4箇所
|
14箇所
|
こども家庭課
|
|
※一時預かり事業
実施箇所数 |
60箇所
|
79箇所
|
こども家庭課
|
|
※病後時保育当事業実施箇所数 |
病児・病後時対応型 |
6箇所
|
13箇所
|
こども家庭課
|
|
体調不良時対応型 |
9箇所
|
16箇所
|
|
※子育て短期支援事業施設数 |
ショートステイ |
8箇所
|
15箇所
|
こども家庭課
|
|
トワイライトステイ |
8箇所
|
14箇所
|
※は全国共通で設定する事業項目
●主な取組
待機児童の解消のための支援
・保育所の整備等により受入児童数を拡大する等、保育需要に適切に対応できるよう支援します。
多様な保育ニーズに対応したサービスの提供のための支援
・市町村と連携し、延長保育、休日保育、病後児保育等、多様な保育ニーズに対応したサービスの提供を支援します。
保育の質の向上や就学前教育の充実のための支援
・研修会の開催等、保育士の専門性を図るとともに、保育所と幼稚園の教育と保育の総合的な提供の推進や、認定こども園の設置促進等、就学前教育の連携を推進し地域の実情に応じた取組を推進します。
(3)児童の健全育成
放課後や週末等の就学児童の安全で適切な遊びや生活の場を確保し、自主性や社会性を培う場の充実を進めるとともに、地域における健全育成の拠点整備等、次代を担う子どもたちが健やかに育つための環境づくりに努めます。
|
施策方向の目標指標 |
現状
(平成20年度) |
目標値
(平成26年度) |
担当課 |
|
※放課後児童プラン |
※放課後児童健全育成事業 |
登録児童数 |
10,035人
|
10,623人
|
こども家庭課
|
|
箇所数 |
204箇所
|
222箇所
|
|
奈良県地域教育力再生事業実施教室箇所数 |
53箇所
|
89箇所
|
人権・社会教育課
|
※は全国共通で設定する事業項目
●主な取組
放課後児童健全育成事業の充実
・労働等で昼間保護者がいない家庭の子どもについて安全性を確保するとともに、遊びを通して自主性や社会性等を培うための事業を充実します。
地域における健全育成の拠点整備の充実
・児童館の運営支援や地域のボランティアの活用を通し、地域における拠点の充実を図ります。
(4)子育て支援のネットワークづくり
様々な子育て支援活動を行う支援者や子育て中の親子の自主的な交流の場である「子育てサークル」のリーダー等に対し、情報交換や課題の共有ができる県域でのネットワークを形成し、地域の子育て支援の輪を広げます。
また、子育て家庭に対し、子どもや子育て支援に関連した幅広い情報を提供します。
|
施策方向の目標指標
|
現状
(平成20年度)
|
目標値
(平成26年度)
|
担当課
|
|
子育てサークル数
|
251団体
|
280団体
|
少子化対策室
|
●主な取組
地域の子育て支援者のネットワークづくりの推進
・子育て中の親子の自主的な交流の場である「子育てサークル」のリーダー等地域の子育て支援者等が情報を交換したり互いに交流したりできる場となる、県域ネットワークの形成を推進します。
地域の子育て支援の情報の提供
・子育て家庭に対し、子どもや子育て支援に関連した福祉・保育・医療・教育等の幅広い情報を、できるだけ分かりやすく、また容易にアクセスできるよう、携帯電話からも検索できるインターネットを活用したポータルサイトにより提供します。
(5)子育てに伴う経済的支援策の充実
子育て家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を目指し、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、医療費や教育費等の子育てに係る費用への助成や奨学金制度等の周知を図ります。また企業や店舗等が子育て家庭へサービスを提供するなど、社会全体で応援する施策を推進します。
財源の確保等を国に要望するとともに、国レベルで抜本的な対策を立てるよう、国に提言していきます。
|
施策方向の目標指標 |
現状
(平成20年度) |
目標値
(平成26年度) |
担当課 |
|
なら子育て応援団 |
利用者登録数 |
2,400人
(H22.2.末)
|
10,000人
|
少子化対策室
|
|
登録団体数 |
637団体
(H22.2.末)
|
1,000団体
|
●主な取組
子育てに係る費用への助成や制度の周知
・医療費や教育費等の子育てに係る費用への助成や、奨学金制度等の周知を図ります。
子育て家庭の生活の安定のための助成
・子どもの健やかな成長のため、子ども手当を支給します。
・生活の困窮の程度に応じた保護費を支給します。
子育て家庭への経済的な支援となるサービスの提供
・企業、店舗等が子育て家庭に対し、料金の割引等のサービスを提供する「なら子育て応援団」事業を展開します。
具体的な事業
(1)地域における子育て支援の充実
|
事 業 名
|
実施主体
|
事 業 概 要
|
担 当 課
|
| 地域子育て支援拠点事業 |
市町村 |
子育て親子の交流の促進や子育て等の相談を行う地域における子育て支援拠点を拡充し、地域における子育てを推進する。
|
こども家庭課 |
| 児童委員・主任児童委員の設置 |
県 |
児童委員・主任児童委員を設置し、地域の身近な子育て相談窓口として、相談活動や情報提供を行う。
児童委員2,025人、主任児童委員215人
|
こども家庭課 |
| 安心子育て支援対策事業 |
市町村 |
「奈良県安心こども基金」を活用し、保育所整備、保育の質の向上のための研修を行い、子育て支援サービスの緊急整備を実施。
|
こども家庭課 |
| 子育て電話相談「安心子育てダイヤル」の運営 |
県 |
育児の悩みや不安などについて、子育ての経験や豊富な知識を持つボランティアグループが電話により相談に対応する。
・相談日:週5日(月・火・木・土・日曜日) ・相談時間:午前10時~午後8時(土・日曜日及び月・火・木曜日が祝日の場合午後1時~午後5時)
|
こども家庭課 |
| 家庭支援電話相談室「子どもと家庭テレホン相談」事業 |
県 |
県中央こども家庭相談センターにおいて、児童と家庭に関する問題について、電話により相談に対応する。
・相談日:毎日(年末・年始の6日間は休み) ・相談時間:平日は午前9時~午後8時 土・日・祝日は午前9時~午後4時
|
こども家庭課 |
| 児童家庭支援センター事業 |
社会福祉法人 |
休日や夜間の相談に応じるなど、地域に密着した相談支援体制を充実する。
設置箇所 2箇所
|
こども家庭課 |
| 市町村体制強化支援事業 |
県 |
児童家庭相談の一義的窓口である市町村の児童家庭相談体制の強化のため、こども家庭相談センターによる支援を行う。
|
こども家庭課 |
| 児童福祉週間(5月5日~11日) の啓発普及 |
県 市町村 |
児童福祉の理念のいっそうの周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を図る。 |
こども家庭課 |
| 地域の子育て力推進委員会の設置 |
県 |
県内関係団体の代表者及び学識経験者等で構成する「奈良県こども・子育て応援県民会議」の中に「地域の子育て力推進委員会」を設置し施策について検討する。
|
少子化対策室 |
| 大学連携地域子育て支援推進事業 |
県 |
地域の子育て支援に取り組む県内の大学と連携し、子育て支援者のスキルアップなどの施策を検討し実施する。 |
少子化対策室 |
| 「なら子育て応援団」事業 |
県 市町村 奈良県こども・子育て応援県民会議 |
県民会議の下に「なら子育て応援団」を設置し、企業・店舗・NPO等が子育て応援団となり、割引などのサービスを行う等、地域が一体となって子育てを応援する県民運動として展開する。
|
少子化対策室 |
| 子育て電話相談事業 |
県 健やか奈良支援財団 |
子育てに関する電話相談窓口を設置する。 |
少子化対策室 |
| 子育て支援者スキルアップ事業 |
県 健やか奈良支援財団 |
子育て支援者のために、子育て支援のための知識等の学びの場と、支援者相互の情報交換や交流の場を提供することで、子育て支援の資質の向上とそれぞれに活動する支援者のネットワークを図る。
|
少子化対策室 |
| ファミリー・サポート・センターの設置勧奨 |
市町村 |
仕事と子育ての両立を図るため、ファミリー・サポート・センターの設置主体となる市町村に対し、設置勧奨を実施する。 |
雇用労政課 |
| 電話教育相談「あすなろダイヤル」 |
県教委 |
子育て、不登校、いじめ等教育に関する様々な相談に対応する「あすなろダイヤル」と全国統一の「24時間いじめ相談ダイヤル」を設置。「24時間いじめ相談ダイヤル」はあすなろダイヤルに転送され対応する。また開設時間帯以外は「奈良いのちの電話」に転送される。 (あすなろダイヤル)・相談日:毎日 ・相談時間:月~金は9時から21時、土・日・祝日は9時から19時
|
教育研究所 |
(2)多様な保育サービスの充実
|
事 業 名
|
実施主体
|
事 業 概 要
|
担 当 課
|
| 預かり保育の推進 |
私立幼稚園 |
幼稚園において、育児と仕事の両立のため幼稚園の通常の教育時間終了後も引き続き預かり保育を行う。
|
総務課 |
| 特定保育事業 |
市町村 |
保護者のいずれもが、一定程度の日時について児童を保育することができないと認められた就学前児童に対する保育に対応する。
|
こども家庭課 |
| 延長保育事業 |
市町村 |
保護者の就労等による開所時間が11時間を超える保育の需用に対応する。
|
こども家庭課 |
| 病児・病後児保育 |
市町村 |
看護師等により病児・病後児・体調不良児に対する一時的な保育や緊急対応を行う。
|
こども家庭課 |
| 休日保育事業 |
市町村 |
日曜・祝日等の保護者の就労等による、休日の保育の需要に対応する。
|
こども家庭課 |
| 一時預かり事業 |
市町村 |
保護者の就労形態の多様化及び、傷病や育児疲れ等に対応するために一時預かり保育を実施する。
|
こども家庭課 |
| 2歳未満児保育実施事業 |
市町村 |
保育所における低年齢児保育の充実を図る。
|
こども家庭課 |
| 保育士、栄養士、児童指導員等児童福祉施設職員等研修 |
県 |
児童福祉施設職員の資質の向上を図るため、児童福祉、保育、看護、給食等に関する専門的知識や技術についての研修を行う。
|
こども家庭課 |
| 安心子育て支援対策事業(再掲) |
市町村 |
「奈良県安心こども基金」を活用し、保育所整備、保育の質の向上のための研修を行い、子育て支援サービスの緊急整備を実施。
|
こども家庭課 |
| 就学前教育連絡調整会議運営事業 |
県 県教委 |
就学前乳幼児の保育と教育の連携強化や子育て支援の充実を図る。(22年度はこども家庭課)
|
こども家庭課
教育研究所 |
(3)児童の健全育成
|
事 業 名
|
実施主体
|
事 業 概 要
|
担 当 課
|
| 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ) |
市町村 |
保護者が労働等により昼間家庭にいない、主として小学校低学年児童について、安全等を確保するとともに、遊びを通じた自主性・社会性・創造性の向上等を図る。
|
こども家庭課 |
| 児童館の運営 |
社会福祉法人 |
社会福祉法人が設置した児童館の運営等に要する経費に補助する。
|
こども家庭課 |
| 地域組織(母親クラブ)活動育成費補助 |
市町村 |
児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民が積極的に参加した地域組織の児童福祉の向上に寄与する活動に補助を行う。
|
こども家庭課 |
| 児童委員・主任児童委員の設置(再掲) |
県 |
児童委員・主任児童委員を設置し、地域の身近な子育て相談窓口として、相談活動や情報提供を行う。
児童委員2,025人、主任児童委員215人
|
こども家庭課 |
| 安心子育て支援対策事業(再掲) |
市町村 |
「奈良県安心こども基金」を活用し、保育所整備、保育の質の向上のための研修を行い、子育て支援サービスの緊急整備を実施。
|
こども家庭課 |
| 地域・家庭教育支援ボランティアシステム |
県教委 |
県と市町村等で実施する「地域放課後子ども教室推進事業」や市町村が独自に実施している「子どもの居場所づくり事業」等に、退職教職員等がボランティアとして協力・支援していただくための人材バンクを運営(登録と情報提供)。
|
人権・社会教育課 |
| 奈良県地域教育力再生事業 |
県教委 |
地域のボランティアの人々の力を借り、子どもたちの「人間力」を育成することを通して、地域の教育力の再生を図る。
|
人権・社会教育課 |
(4)子育て支援のネットワークづくり
|
事 業 名
|
実施主体
|
事 業 概 要
|
担 当 課
|
| 子育てホームページ運営事業(再掲) |
県 健やか奈良支援財団 |
子ども・家庭に関する情報を横断的、総合的、一元的に提供するポータルサイト「子育てネットなら」の管理・運営等を行い、子ども・家庭に関する幅広い情報提供を行う。
|
少子化対策室 |
| 子育て支援者スキルアップ事業(再掲) |
県 健やか奈良支援財団 |
子育て支援のための知識等の学びの場と、支援者相互の情報交換や交流の場を提供することで、子育て支援の資質の向上とそれぞれに活動する支援者のネットワークを図る。
|
少子化対策室 |
(5)子育てに伴う経済的支援策の充実
|
事 業 名
|
実施主体
|
事 業 概 要
|
担 当 課
|
| 私立学校教育経常費補助事業 |
県 |
私立学校の教育条件の維持向上、学費負担者の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高める。
高等学校15校 中等教育学校1校 中学校10校 小学校5校 幼稚園41園
|
総務課 |
| 私立高等学校授業料軽減補助事業 |
県 |
私立高等学校に在学する生徒の学費負担者の経済的負担の軽減を図る。
|
総務課 |
| 新 私立高等学校等就学支援金事業 |
県 |
私立高校生等のいる世帯に対して、国公立高校生授業料相当額と同等額(低所得者世帯に対しては増額)を助成する。
|
総務課 |
| 生活福祉資金貸付事業 |
社会福祉協議会 |
低所得者等に対し、高等学校等への修学経費(修学費、支度費)の貸付を行う。
|
地域福祉課 |
| 生活保護費の支給事業 |
県 |
資産、能力すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施する。
|
地域福祉課 |
| 乳幼児医療費助成事業 |
県 市町村 |
乳幼児を養育している者に対し、その乳幼児の医療費の一部を助成している市町村に対し補助することにより、乳幼児の健康の保持及び福祉の増進を図る。
|
保険指導課 |
| 子ども手当の支給 |
市町村 |
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象に、一人につき月額13,000円を支給する。
|
こども家庭課 |
| 「なら子育て応援団」事業(再掲) |
県 市町村 奈良県こども・子育て応援県民会議 |
県民会議の下に「なら子育て応援団」を設置し、企業・店舗・NPO等が子育て応援団となり、割引などのサービスを行う、地域が一体となって子育てを応援する県民運動として展開する。
|
少子化対策室 |
| 未熟児養育医療給付事業 |
県 |
入院養育を必要とする未熟児に対し、その治療に要する医療費について保険適用後の自己負担額の一部を公費負担する。
|
保健予防課 |
| 高等学校等奨学金貸与事業(修学支援奨学金) |
県教委 |
修学の奨励と教育の機会均等を図るため、勉学の意欲がありながら経済的な理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対し、奨学金を貸与する。(収入要件あり)
|
学校支援課 |
| 育成奨学金貸付事業 |
県教委 |
修学の奨励と教育の機会均等を図るため、勉学の意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対し、奨学金を貸与する。(収入要件と成績要件あり)
|
学校支援課 |
「児童・生徒等に対する修学等援助事業一覧」の作成・配布事業
|
県教委 |
援助事業内容についての一覧表を作成、ホームページで公開する。
|
学校教育課 |
|
|
奈良県こども・子育て応援プラン
奈良県健康福祉部こども家庭局少子化対策室
|