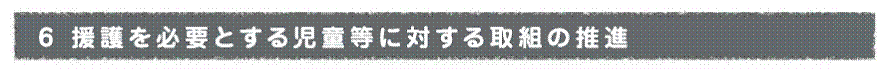
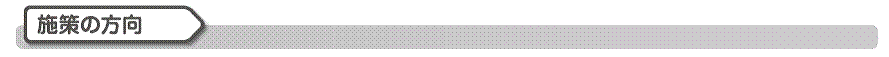
(1)養育が困難な家庭への早期支援
子育てに不安を感じたり、養育が困難になっている家庭に対し、早期に支援を行います。
●主な取組
健康診査等の場を通しての早期支援の実施
・健康診査等の場を活用し、様々な原因で養育が困難になっている家庭や出産後まもない時期の親に対して、保健指導や育児指導等を行うとともに、市町村の母子保健事業の充実を支援します。
(2)児童虐待防止対策の充実
児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応等、それぞれの段階における適切な対応や支援を、市町村や関係機関と連携を図りながら推進します。
|
施策方向の目標指標 |
現状
(平成20年度) |
目標値
(平成26年度) |
担当課 |
|
要保護児童対策地域協議会(ネットワーク)設置市町村数 |
30市町村
|
39市町村
|
こども家庭課
|
●主な取組
こども家庭相談センターの機能強化
・一時保護児童への支援や重篤なケース、DV家庭の子ども等、長期間にわたる支援や専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応が行えるよう、こども家庭相談センターの機能を強化します。
市町村や関係機関との連携の推進
・市町村職員に対する研修や情報の提供により、市町村の体制を強化します。
・市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会(市町村域児童虐待防止ネットワーク)の設置促進や機能強化を図ります。
・DV防止のためのセミナーや相談を実施します。
(3)社会的養護体制の充実
社会的養護体制の質・量ともに充実を図ります。
個々の子どもにあった自立を支援するため、里親制度をはじめとする家庭的養護を推進し家庭支援機能を強化します。
また、子どもの権利擁護を強化します。
|
施策方向の目標指標
|
現状
(平成21年度)
|
目標値
(平成26年度)
|
担当課
|
|
養育里親登録数 |
50人
|
85人
|
こども家庭課
|
●主な取組
家庭的養護の推進
・新規里親を開拓し支援することによって、里親制度の充実を図り里親への委託を推進します。
・家庭的養護の一形態として、ファミリーホーム等の設置を促進します。
施設機能の見直し
・心理的ケアの充実や家庭的養護の推進などケア単位の小規模化を図ります。
・個々の児童に応じたケアができるように、一時保護所の充実を図ります。
家庭支援機能等の強化
・家庭支援機能を強化するため、こども家庭相談センターの体制強化とともに、市町村や関係機関との役割分担及び連携を推進します。
自立支援策の強化
・社会的養護の下で育った子どもが施設を退所後等に、地域で自立した生活を送ることができるよう、気軽に相談できる拠点など必要な支援体制を整備します。
・関係機関と連携し、虐待を受けた子どもやDV被害者の同伴児童等に対し、一時保護や自立支援のための相談等を行います。
人材確保のためのしくみの強化
・社会的養護の担い手となる職員及びその職員の専門性を確保するため、研修体制を整備します。
子どもの権利擁護の強化
・子どもの権利擁護を強化するため、被措置児童等虐待に対する適切な対応のほか、ケアの質の向上に取り組みます。
(4)ひとり親家庭の自立支援の推進
ひとり親家庭の子どもの健全な育成を目指し、ひとり親の自立のためのきめ細やかな就労支援策を展開するとともに、総合的なひとり親家庭対策を積極的に進めます。
|
施策方向の目標指標 |
現状
(平成20年度) |
目標値
(平成26年度) |
担当課 |
|
母子・スマイルセンターのバンク登録者の就業率 |
39.3%
|
50%
|
こども家庭課
|
●主な取組
母子家庭等の自立の促進
・就労相談や講習会、ITを用いた自営型の在宅就業支援等に取り組みます。
・子育て支援、生活支援、養育費の確保等に取り組みます。
(5)子どもの貧困対策の推進
「子どもの貧困」について、奈良県のデータや実態を分析し今後の対策を検討します。
●主な取組
子どもの貧困対策の調査検討
・子どもの貧困について、県庁内の関係課で構成するワーキンググループを設置し既存のデータや現場の実態を分析し、今後の施策を検討します。
援護が必要な子どもや家庭への自立等の支援
・援護が必要な子どもや家庭のため、経済的支援や保育所への助成等を実施します。
(6)障害児施策の充実
障害のある子どもやその保護者等が地域で安心して生活していくため、一人ひとりの障害の特性、ライフステージにより変化するニーズ等に応じた多様な支援体制の充実を図ります。
|
施策方向の目標指標
|
現状
(平成20年度)
|
目標値
(平成26年度)
|
担当課
|
|
障害児等療育相談実施箇所数 |
4箇所
|
6箇所
|
障害福祉課
|
|
個別の指導計画を作成している学校の割合 |
85%
|
95%
|
特別支援教育
企画室
|
●主な取組
相談支援体制等の充実
・障害のある子どもやその保護者等が地域で安心して生活するため、相談や就学指導等の体制を充実します。
発達障害者への支援体制の充実
・発達障害に関しては、社会的な理解が得られるよう適切な情報の周知を図り、関係機関や保護者に対する専門的情報の提供や支援手法の普及を推進するとともに、障害特性等に応じた福祉サービスの充実を図ります。
重症心身障害児の医療ケア体制の充実
・重症心身障害児施設の体制の充実、医療ネットワークの構築等を図ります。
また、障害児を介護する家族のレスパイト支援(疲れをいやす等の支援)体制の充実を図ります。
特別支援教育体制の充実
・特別支援学校については、その専門性を活かし、小・中学校等の教員への協力・支援、地域の保護者等への相談支援、小・中学校等における障害のある子どもへの教育的支援等、地域における特別支援教育のセンター的役割を果たすよう努めます。
医療費や手当等の支援
・生活の向上等のための手当の支給、健康の保持及び、福祉の増進のための医療費の補助に対する支援等を行います。
(7)外国人の子育て家庭への支援
NPOやボランティア、関係機関と連携し、日本に居住する外国人の子どもにとって言葉や生活習慣の違いが地域社会で生活する上で支障とならないよう、また、様々な偏見や差別を受けることがないよう支援します。
●主な取組
言葉や暮らしへの支援
・子育て情報を含む多言語による生活情報の提供や各種相談等の支援に努めます。
国際理解への交流等事業
・国際交流員や留学生の学校等への派遣等、相互理解を図るための施策を推進します。
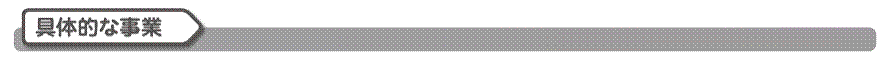
(1)養育が困難な家庭への早期支援
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 未熟児・低体重児支援事業 (未熟児訪問指導) |
県 |
医療機関と連携をとりながら、未熟児を養育する家庭を早期に把握し、家庭訪問等により必要な保健指導及び育児支援を行う。
|
保健予防課 |
| 1歳6か月児健診・3歳児健診の充実支援 |
県 |
母子保健推進会議等で、施策を検討し、市町村母子保健事業の充実を図る。
|
保健予防課 |
(2)児童虐待防止対策の充実
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 児童虐待防止支援事業 |
県 |
児童虐待防止への取組を強化するため、中央こども家庭相談センターに24時間相談体制を整備するなど、支援体制の核となるこども家庭相談センターの機能を強化する。
|
こども家庭課 |
| 「みんなで見守る」児童虐待の防止・支援事業 |
県 |
児童虐待の総合的な見守り体制の確立をめざして、市町村、関係機関等の意識改革・意識向上、児童虐待対応スキルの向上のために、スーパーアドバイスチームの派遣や、基礎・専門研修を行う。
|
こども家庭課 |
| 女性に対する暴力防止対策事業 |
県 |
DV、性犯罪、セクハラ等の女性に対する暴力の根絶をめざし、県民の意識啓発、被害者支援に取り組む。
|
男女共同参画課 |
| 女性センター相談事業 |
県 |
女性の様々な問題や悩みについて、電話や面談による相談を行う。
・女性相談機関交流会の開催
・相談員研修会の開催
|
男女共同参画課 |
| DV被害者支援を考える講座 |
県 |
DVの実態、被害女性の心理、暴力をふるう側の問題等を学び、社会全体で被害者を支援していく方法について男女ともに考える。(女性センター講座・セミナー事業の一部)
|
男女共同参画課 |
(3)社会的養護体制の充実
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 要保護児童対策地域協議会(市町村域児童虐待防止ネットワーク)の整備 |
県 |
市町村の家庭児童相談の体制強化を図るため研修会を実施する。
|
こども家庭課 |
| 要援護家庭支援の推進 |
県 |
保護児童、DV被害者及び同伴児童の増加に伴う定員超過に対応するため、児童福祉施設に委託して一時保護を実施する。
|
こども家庭課 |
| 女性相談対策事業 |
県 |
要保護女子等に対する緊急保護及び短期間の更生指導、生活指導等を行う。
|
こども家庭課 |
| 被虐待児一時保護事業(再掲) |
県 |
虐待を受けた子どもの生命安全を確保したり、処遇指針を定めるため行動観察する等を目的として、子どもを一時保護所に一時保護したり、適当な者に一時保護を委託する。
|
こども家庭課 |
| DV被害者支援事業 |
県 |
DV被害者及び同伴児童に対する自立支援のため、相談用務の充実及び関係機関とのネットワークの構築を図る。
|
こども家庭課 |
| 里親推進事業 |
県 |
里親制度に対する社会の認識を深め、里親登録と委託を推進する。里親の養育技術向上のための研修実施や、里親が受託しやすい環境づくりを行い、里親への支援を推進する。
|
こども家庭課 |
| こどもの安らぎ・癒し環境検討事業 |
県 |
中央こども家庭相談センターにおいて、要保護児童等への心温まるきめ細やかな対応の推進のため、施設整備を前提に、ケアのあり方等を検討する。
|
こども家庭課 |
| 精華学院整備事業 |
県 |
耐震化及び老朽化に対応し、精華学院(児童自立支援施設)の本館の改築、寮の改修、プールの改築等を実施し、入所児童の生活・学習環境の改善を図り、自立支援を推進する。
|
こども家庭課 |
(4)ひとり親家庭の自立支援の推進
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 母子医療費助成事業 |
県 市町村 |
母子家庭等に医療費の一部を助成している市町村に対し補助することにより、母子家庭等の健康の保持及び福祉の増進を図る。
|
保険指導課 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 |
県 |
母子家庭、寡婦に対して、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、その扶養している児童の福祉の増進のため、貸付を行う。
|
こども家庭課 |
| 母子家庭等就業・自立支援センター事業 |
県 |
母子家庭の母親等の、就業相談、就業情報の提供、講習会の開催、自立支援プログラム策定事業を実施する。
|
こども家庭課 |
| 自立支援教育訓練給付金事業 |
県 |
母子家庭の母親で、職業能力の開発を自主的に行う者に対し、教育訓練終了後給付金を支給する。
|
こども家庭課 |
| 母子家庭等高等技能訓練促進事業 |
県 |
就職に際し有利な資格取得を容易にするため修業期間中の一定期間に生活費を支給する。
|
こども家庭課 |
| 母子家庭等日常生活支援事業 |
県 |
ひとり親家庭や寡婦に対し、介護や保育サービス等の日常生活支援を行い、ひとり親家庭の生活基盤の安定を図る。
|
こども家庭課 |
| ひとり親家庭支援事業 |
県 |
戸別訪問による相談や在宅就業を支援
|
こども家庭課 |
| 児童扶養手当の支給 |
県 市等 |
父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図る。平成22年8月より父子家庭に対しても支給する。
|
こども家庭課 |
| 新 就労困難者在宅就業支援事業 |
県 |
ひとり親家庭、障害者の就労困難者に対して、ITを用いた訓練を実施し、自営型のテレワークの普及の支援を図る。 |
雇用労政課 |
(5)子どもの貧困対策の推進
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 「子どもの貧困」対策県庁内ワーキングの設置 |
県 |
基準そのものも存在せず、実態についても不明である「子どもの貧困」について関係各課とともに、既存データや現場の実態などで調査分析し今後の対策につなげる。
|
少子化対策室 |
| 家庭支援推進保育事業費補助 |
県 |
家庭環境など、保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所に対する助成
対象保育所数 26箇所
|
こども家庭課 |
| 児童扶養手当の支給(再掲) |
県 市等 |
父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図る。平成22年8月より父子家庭に対しても支給する。
|
こども家庭課 |
| 子ども手当の支給(再掲) |
市町村 |
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象に、一人につき月額13,000円を支給する。
|
こども家庭課 |
(6)障害児施策の充実
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 心身障害児教育振興事業 |
県 |
心身障害児教育に必要な経費について学校法人に補助を行い、心身障害児の私立幼稚園への就園促進を図る。
|
総務課 |
| 発達障害者支援センター運営事業 |
県 |
発達障害のある児(者)とその家族に対する総合的な支援を行う。
|
障害福祉課 |
| 障害児福祉手当の支給 |
県 市町村 |
重度の障害を有する児童に手当を支給することにより、在宅障害児の生活の向上を図る。
|
障害福祉課 |
| 重症心身障害児(者)通園事業 |
県 中核市 |
障害児施設に通園することにより、重症心身障害児に日常生活動作や運動機能に係る療育訓練等を行う。
|
障害福祉課 |
| 障害児等療育相談 |
県 中核市 |
専門的な療育指導、相談等が受けられるよう療育機能の充実を図る。
|
障害福祉課 |
| 重症心身障害児(者)医療ケア推進事業 |
県 |
在宅重症心身障害児(者)に対する医療、介護、看護等が綿密に連携した医療ネットワークの構築及び民間重症心身障害児施設の看護師確保を図る。
|
障害福祉課 |
| 心身障害者医療費助成事業 |
県 市町村 |
心身障害者に対し、その医療費の一部を助成している市町村に対し補助することにより、障害者の健康の保持及び福祉の増進を図る。
|
保険指導課 |
| 特別児童扶養手当の支給 |
県 市町村 |
家庭において介護されている障害を有する児童に対し手当を支給する。
|
こども家庭課 |
| 障害児保育受入促進事業(再掲) |
市町村 |
障害児をより多く受け入れ、かつ障害児に手厚いケアを実施する保育所へ補助を行い、障害児の受入促進を図る。
|
こども家庭課 |
| 育成医療給付事業 |
県 |
肢体不自由、視覚障害等で入院治療等を行うことにより確実な治療効果が期待できる児童に対し、その治療に要する医療費について保険適用後の自己負担額の一部を公費負担する。
|
保健予防課 |
| 教育相談体系化推進事業 |
県教委 |
市町村の相談支援体制及び就学指導体制の整備充実を支援する。
|
特別支援教育企画室 |
(7)外国人の子育て家庭への支援
| 事 業 名 |
実施主体 |
事 業 概 要 |
担 当 課 |
| 外国文化紹介出前講座開催事業 |
シルク財団 |
国際交流員や留学生等が国際交流や多文化理解に関するイベント講師に出向き、外国文化の紹介を行う。
|
国際観光課 |
| 在住外国人向け多言語情報提供事業 |
シルク財団 |
在住外国人にとってニーズの高い生活に関わる基本的な情報をホームページ上で多言語(英、中、葡、ハングル、日)により提供する。
|
国際観光課 |
| 在住外国人相談事業 |
シルク財団 |
窓口において生活に必要な各種情報の提供と専門相談機関の紹介などを多言語(英・中・葡)で行う。
|
国際観光課 |
| 日本語習得のための常勤及び、非常勤講師の配置事業 |
県教委 |
生活習慣等の違う異国の地で様々な不安を抱えながら学校生活を送っている児童・生徒の日本語習得、及び学習を支援するため、常勤及び非常勤講師を配置する。
|
教職員課 |
| 外国人児童・生徒受入支援者派遣事業 |
県教委 多文化共生フォーラム奈良 |
多文化共生フォーラム奈良と協働し、日本の学校に初めて入学・編入学する児童生徒を受け入れる小中学校に支援者(初期対応コーディネーターと通訳者)を派遣する。
|
人権・社会教育課 |
| 日本語指導資料の作成・配布事業 |
県教委 |
学校での日常生活に順応し、日本語での教科学習に対応できるよう、各国語でテキストを作成し必要な学校に配布する。
|
人権・社会教育課 |
| 母語通訳者派遣事業 |
県教委 |
生徒の進路保障や生活指導上の諸課題を解決するため、三者懇談や家庭訪問の際に母語通訳者の派遣を行う。
|
人権・社会教育課 |
|
|
奈良県こども・子育て応援プラン
奈良県健康福祉部こども家庭局少子化対策室
|