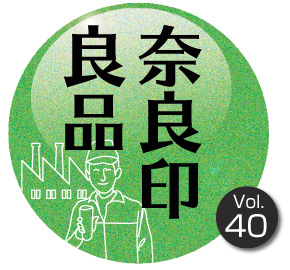 |
あらゆる分野で活躍できる
スクリーンを作り続けます |
|

人と「向き合う」ことを大切にされているので、社内の風通しも良く、仲の良い社員の皆さん。

お客さまの用途に合わせたいろいろなスクリーン製品
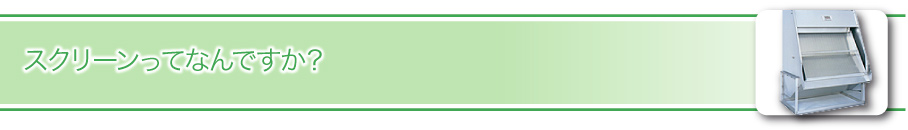
スクリーンと聞くと、一般の人は映画のスクリーンを思い浮かべるかもしれませんが、「混合物を除く(分離)」・「大きさによって分ける(分級)」などを行うための部品・装置をスクリーンといいます。例えば、水流を使って昆布の佃煮から糸くずや髪の毛などを除いたり、トンネルの掘削時に出る土砂を分級するための「フィルター」と思ってもらえばわかりやすいでしょうか。 
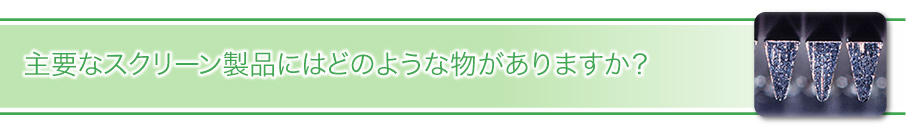
当社の主要製品の一つに、ウェッジワイヤースクリーンがあります。断面が逆三角形のワイヤーを等間隔に並べて製造しており、目詰まりが少なく、強度・耐久性にも優れているのが特長です。
この製品以外にもいろいろな形状・用途の製品があり、さまざまな産業分野で使われているんですよ。

業務の改善を進めるのに、PDCAサイクル(ISO14001の基本構造)で計画から見直しまでを繰り返し、業務の継続的な改善を行うことが有効だったんです。現在は職人の経験に加え、大学等と連携して製品の効率性や精度をより詳しく数値化し、お客様にわかりやすく示しています。
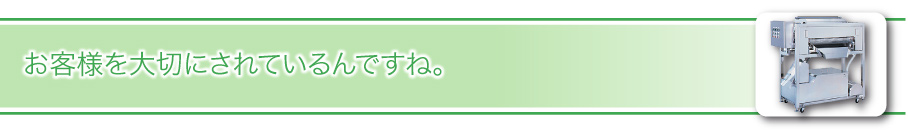
当社が60年近く続いているのも、お客様と真摯(しんし)に向き合い、良い関係を築いてきたからだと思っています。要望をお聞きすることはもちろんですが、それだけでなく、新しい提案を行って、お客様と一緒により良いオリジナルの製品を作っているんです。全社員がこういった姿勢で仕事に取り組んでいます。

今年度の定期採用は終了してしまいましたが、飛び込みで自分を売り込んでくれるような人は大歓迎です。また、当社は文系や普通科の高校を卒業した人でも、やる気があれば設計や製造などいろいろな業務に挑戦できる、とてもやりがいのある会社です。明るく、気力のある方をお待ちしています。

スクリーンの目をさらに細かくするなど、今以上に技術力を高めたいですね。そうすることで、さらなる提案が可能となり、海外における水問題や新しいエネルギーの分野などで、より広く社会貢献ができればと考えています。
東洋スクリーン工業株式会社

「常に自己研鑽し、創意工夫していくことが大切」と語る
代表取締役社長 廣濱(ひろはま) 武雄(たけお)さん
分離・分級・濃縮・脱水や環境保全に関する部品および機器・装置等の企画・製造・販売を行うメーカー。数マイクロメートルという目開きでスクリーンを作る高い技術力が認められ、近畿経済産業局が「KANSAIモノ作り元気企業」に選定。海外の展示会にも積極的に出展するなど、さらなる事業分野の拡大を目指す。
所 斑鳩町幸前2-10-6
TEL 0745‐70‐1711
FAX 0745‐70‐1712
URL www.toyoscreen.co.jp/
|
|
< 前回(2013.10月号 vol.39)へ 次回(2014.1月号 vol.41)へ >