「E-夢 はっしん!」
平成27年11月1日(日曜日)
≪第 245 号≫
このメールマガジンを保存いただく方法は、 こちらをご覧ください。
このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。
レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、 こちらをご覧ください。
発行:奈良県教育委員会事務局企画管理室
仕事の塩梅
県立教育研究所
参事 土居 正明
今年は若い先生方と話をする機会が多く、少しうれしい。いい先生に育ってほしいと、つい自分の経験を話してしまう。
そんな折、「うちの梅干しの味を伝えたいけどなあ。」と、83歳になる母の言葉が胸をついた。わが家の老いた梅の木からは肉厚の梅の実がとれる。洗った後、爪楊枝で掃除をし、漬けと天日干しを繰り返す。その後、陶器の壺に紫蘇と塩を入れて漬け込むのである。どこにも売っていない独特な味と香りをもつわが家の梅干しができる。書けば2行ほどの作業を毎年見ていて、解っているつもりになっていた。しかし、今年体調を崩した母の代わりにやろうとしたが、実は一緒に作業をしたことがなく、ノウハウや実感がない。何も知らないということに気付かされるばかりで、ネットで調べる始末であった。自分の舌はわが家の味を覚えていても、同じものができないのだ。
話は変わるが、『創業300年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか』(東洋経済編)に、「なぜ長寿企業は人材育成が上手なのか」という文章を見つけたので紹介を兼ねて書きたい。
日本は世界的に見て長寿企業大国である。その中で創業300年を超え、年商50億円を超える企業69社を、近年のキーワードで持続的発展を意味する「日本型サスティナブル企業」と名付け、長く繁栄する秘訣について述べている。300年前といえば、赤穂浪士の討ち入りがあったり、将軍吉宗が享保の改革を行っていた頃であり、中には大坂夏の陣の頃の創業などという企業も含まれる。度重なる社会の仕組みや価値観、また産業構造の革命的変容を経験しているはずだ。長く栄える要素はいろいろあるだろうが、人材育成は重要な要素で、伝統的なノウハウ、徒弟制度的な仕組みとそれを支援する制度等をもつところが多い。仕事を教えるだけでなく、それぞれの企業がもつ社風やこだわりを徹底的に身に付けさせるところが多いようだ。
組織学習の場である会社に新しいメンバーが加わると、熟達者=中心的存在のメンバーである先輩社員や経営者、顧客を含めたステークホルダー(利害関係者)全員が教師になり、新メンバーを含めた学習が回り始める。ステークホルダーを教師にして、社会的実践を通じて学び成長することでアイデンティティを確立し、新参者から価値観やコア能力を体現できる組織の中心的存在に育っていくというのだ。
京都の日本酒メーカーは、酒造り研修を行っている。大きなメーカーでは自社の本業である酒造りについて、製造部門以外のものはほとんど見たことがなく、どういうものであるかを新入社員のときに知ることは、たとえ数日でも強い体験となる。製造部門の古参社員に現場で教えられることは、研修会場で聞くより何倍ものリアリティがあると口をそろえ、この日本酒メーカーの一員になったことを実感する。現代的にいうと正統なOJTだろう。あと、社外講師による研修や社外留学で、新しい知見を取り入れ、外から自社を見るというところは、off-JTに当たるのだろうか。
人材育成に成功している企業は組織として強靱で、困難を乗り越え、新しい時代に対応していく大きな力を手にする。持続的発展の基盤といえるのだろう。
今まで子どもたちをどうするか、学校をどうするか、ばかりを考えてきた気がする。伝統的で、変化が激しく、時代の要請が強く、やりがいのある職業である教職員の人材育成という難しさと楽しさに、改めて勉強しなければと思いながら、先生方がいい塩梅で仕事ができるようにと祈っている。
【1】平成27年度地方教育行政功労者表彰について
<教職員課>
地方教育行政功労者表彰は、地方教育行政においてその功労が特に顕著な教育委員会の委員または教育長が文部科学大臣によって表彰されるものです。今年度、県内からは次の3名の方々が、10月6日(火曜日)に文部科学省において表彰されました。(年齢と主要職歴は平成27年8月1日現在のものです)
高取町教育委員会教育長 嶋田 良文(しまだ よしゆき)さん
(73歳 奈良県高市郡高取町在住)
教員としての豊富な経験、高い識見を生かしながら、地域や教育現場の声を重視し、髙取町の教育環境の充実と健やかな子どもの育成に努めてこられました。平成13年には文部科学大臣より学校保健及び学校安全表彰を受けておられます。
三宅町教育委員会委員 岡本 真寿美(おかもと ますみ)さん
(52歳 奈良県磯城郡三宅町在住)
地域が学校を支える教育を提唱し、学校・地域パートナーシップ事業に精力的に取り組んで来られました。平成15年の委員就任から今日に至るまで、三宅町の教育環境の充実と発展に取り組んでこられました。
下北山村教育委員会委員 山本 博久(やまもと ひろひさ)さん
(78歳 奈良県吉野郡下北山村在住)
児童数の減少がすすむ地域で、小学校の統合や「山村留学制度」の導入に尽力し、大きな成果をもたらされました。自ら足を運び教職員やPTA、地域住民の意見を熱心に聴取し、下北山村の教育環境の充実、発展に尽力されました。
※お問い合わせ先
教職員課 定数管理係
TEL 0742-27-9805
【2】平成27年度奈良県公立学校優秀教職員表彰について
<教職員課>
平成27年10月29日(木曜日)、奈良県庁において、平成27年度奈良県公立学校優秀教職員の表彰を行いました。
県内の市町村教育委員会教育長及び県立学校長から推薦のあった「奈良県公立学校優秀教職員表彰候補者」について、外部委員7名で構成する「奈良県公立学校優秀教職員表彰選考委員会」での選考を経て、13名(小学校6名、中学校3名、県立学校4名)の教職員を県教育委員会教育長が表彰しました。
※お問い合わせ先
教職員課 小中人事係・県立人事係
TEL 0742-27-9846
【3】「みんなあつまれ! いのち かがやき フェスティバル」の開催について
<企画管理室>
平成27年10月24日(土曜日)・25日(日)、うだ・アニマルパークにおいて「みんなあつまれ! いのち かがやき フェスティバル」を開催し、両日で6,130人の方々が来場されました。
このイベントは、世代を超え、子どもたちや保護者・地域の方々、県内の学校・教育関係者が、うだ・アニマルパークに結集し、いのちの大切さをテーマにした様々な体験や心の交流を通して、「いのち」「絆」「ぬくもり」の大切さが実感できる機会を提供し、子どもたちをはじめとする県民の思いやりの心を育み、規範意識、社会性を高めることを目的としたものです。
※お問い合わせ先
企画管理室 企画法令係
TEL 0742-27-9830
【4】重要文化財 丹生神社本殿の修理が完成しました
<文化財保存事務所>
平成27年2月から着手しました重要文化財、丹生神社本殿(にうじんじゃほんでん)建造物保存修理事業が竣工しました。
くわしくはこちら
※お問い合わせ先
文化財保存事務所 事業係
TEL 0742-27-9865
五條高等学校賀名生(あのう)分校の取組である「北海道余市町における農業実習」が50周年を迎えられました。
***************************************************
半世紀の絆
五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校
教頭 田村 隆眞
広大な大地と澄みきった空、生き生きとして荒々しい北海道の自然を生徒たちにも見せてやりたい。故御勢久右衛門先生のこの熱い思いから始まった賀名生分校北海道現場実習が、今年50周年を迎えた。この間、北海道余市町の農家(のべ400軒)でフロンティア精神を学んだ生徒は男子472名と女子320名の計792名。昭和41年、農家の後継者で屈強な男子生徒11名の30日間の実習に始まる。ニッカウヰスキーで有名な余市町は、北海道でも有数の果樹栽培の地であり、西吉野の柿栽培にその技術は生かされるであろうと選ばれたのだという。
毎年4年生は農家に住み込み、早朝からりんごの袋がけ、トマトやサクランボの収穫、ワイン葡萄の種抜き処理などを行う。生徒たちにとって、家庭を離れた見知らぬ土地での生活と農作業は精神的、体力的にも厳しい10日間だったことだろう。
生徒は壮行会で、「期待より不安が大きいが、50年続いた重要な行事であり頑張ってきたい。」と述べ旅立った。
私も生徒たちの旅立ちから一週間後の7月11日、余市の地を踏んだ。すぐさま実習農家に挨拶に訪れ生徒を探すが、農地がとにかく広くなかなか見つけることができない。やっとのことで探し当てると、生徒は学校では見せることのない顔つきで黙々と農作業を行っている。その生徒の背中を見て、北海道の自然が、辛抱強く寛大な心で支えてくださる農家の皆さんが、そしてこの経験が、生徒を成長させてくれていると強く実感した。今年度は7名が5軒の農家にお世話になった。ある葡萄農家には44年もの長きにわたり生徒を受け入れていただいているが、50年、半世紀にも及ぶこの実習は、フロンティア精神の息づく余市町や受け入れ農家の献身的な取り組み、そして五條市の理解と協力があってこそ続けてこられたのであると身にしみて感じる。
私は旅立ちの際、「50年という節目の年に参加できることを幸運に思い、置かれた場所で精一杯努力し、その成果を獲得してほしい。」と生徒たちを激励した。余市の地から戻った彼らの焼けた顔には、出発時には見られなかったある種の自信を見て取ることができた。
<実習風景>
 |
50周年記念交流会には、余市町長はじめ町関係者、受け入れ農家など30名、そして五條市長はじめ市関係者、卒業生、旧職員など51名が参加し、盛大かつ和やかな会となった。 |
県立高田高等学校の小林広佳さんは、高校生平和大使の一員として、8月にスイスで開かれた国連軍縮会議の場でスピーチをされました。
***************************************************
高校生平和大使 -世界で感じてきたこと-
県立高田高等学校
2年 小林 広佳
私は第18代高校生平和大使の一員として、8月17日から20日までスイスのジュネーブを訪問しました。その主たる目的は、国連軍縮会議を傍聴し、核兵器の廃絶を世界に訴えるスピーチをすること、唯一の戦争被爆国である日本国民の世界平和に対する願いを伝えること、そして高校生1万人署名活動により集まった署名を国連に届けることでした。
国連でのスピーチには、平和大使21人一人一人が最大限の準備と努力をして臨みました。カンパをしてくださった方々、署名をしてくださった164,176人の方々、高齢によって直接思いを伝えられない被爆者の方々、みんなの平和を願う強い思いを国連の場で伝え、世界に発信することができました。
今回のスイス訪問日程の中で、関係機関等も訪問しました。最も感動したのは、平和を願う人々が集まっているある会場で、全員が手を繋ぎ、心を一つにして、「We shall live in peace」を歌った時のことでした。その時、私は国や言語や文化、政治体制等が違っていても、一人一人の心が繋がることで世界は必ず一つになれると思いました。
私は今回、国連平和大使としてスイス訪問という貴重な経験をさせていただきました。支えてくださった全ての方々に感謝するとともに、その思いや願いに応えさせていただくために、生涯をかけて活動を続けていきたいと思います。被爆者の高齢化や若者の関心の薄さが問題になっている中で、核兵器の廃絶や平和の大切さを、日本だけでなく世界に訴え続け、人々の関心や意識を高めていきたいと思います。21世紀の未来を創る者として、平和な世界を築くには一人一人がこれからどうしていくべきかを考えてもらえる活動を続けていきたいと思います。

<スピーチの様子> |

<国連欧州本部内にて> |

<国連欧州本部前にて> |
<学校教育課>
今回は、平成28年度高校入試に関する情報をQ&A形式でお届けします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【Q1】 平成28年度県立高校の募集人員は、昨年度と変更になっていますか。
→A
県立高校入学者募集人員は、県内中学校の卒業予定者数や中学校3年生を対象とした進路希望調査等を基にして算出しています。
平成28年度の県立高校入学者募集人員については、平成27年度に比べて全日制課程では、4クラス、160人の減となっています。
募集人員を減ずる高校は、平城高校普通科(教育コース以外)、郡山高校普通科、橿原高校普通科、榛生昇陽高校普通科(総合選択コース)です。
定時制課程、通信制課程については、平成27年度の募集人員と変更はありません。
各校の募集人員については、こちらをご覧ください。
【Q2】 一般選抜や二次募集の募集人員は、いつ発表されますか。
→A
平成28年度の一般選抜の募集人員については、特色選抜の合格発表が行われる平成28年2月26日(金曜日)に発表します。当日の午後6時ごろに、学校教育課のWebページ「公立高校入試出願・実施状況等」に掲載しますので、ご覧ください。
また、二次募集については、一般選抜の合格発表が行われる平成28年3月17日(木曜日)に発表します。当日の午後6時ごろに、学校教育課のWebページ「公立高校入試出願・実施状況等」に掲載しますので、ご覧ください。
【Q3】 各校の平成27年度の出願の状況は、どうすれば分かりますか。
→A
平成27年度の特色選抜や一般選抜などの出願者数は、学校教育課のWebページ「公立高校入試出願・実施状況等」に掲載しておりますので、ご覧ください。
平成28年度入学者選抜の日程、入学者選抜実施要項及び入学者選抜概要は、学校教育課のWebページ「高校入試」に掲載しています。そのほかに、高校進学に関して次のような情報も掲載していますので、活用してください。
●公立高等学校・特別支援学校紹介
学校別に掲載してあります。学校の所在地や特色、行事、部活動、進路状況、制服など、写真入りで様々な情報が紹介されています。
*担当:学校教育課学事係(0742-27-9851)
平成27年度青翔中学校第2回学校見学会「LOOK!!青翔」の実施について
青翔中学校では、小学生の進路決定に役立つよう、本校の特色や入学者選抜について説明するとともに、模擬授業や体験、施設見学などをとおして本校への理解を深めていただくため、学校見学会「LOOK!!青翔」を開催します。
今回の見学会では、9月の文化祭で披露した、中学1年生による英語紙芝居「雄略天皇と一言主の物語(The Legend of Emperor Yuryaku and Hitokotonushi)」をご覧いただく予定です。地域に伝わる昔話を英訳し、紙芝居の絵も自分たちで考えて作製しました。全員がそれぞれの分担の英語を暗誦し、大変好評でした。青翔中学校での学習の成果の一端をご覧ください。
(1)対象 小学校5、6年生の児童とその保護者、小学校教員及びその他教育関係者
(2)会場 奈良県立青翔中学校・高等学校
〒639-2200 御所市525番地 Tel.0745-62-3951
(3)日程 平成27年11月14日(土) 9時00分 ~ 11:30 [受付8時40分~9:00]
9時00分 ~ 10:00 全体説明
青翔中学校についての説明
入学者選抜についての説明
10時10分 ~ 11:30 英語紙芝居、生物実験・観察、施設見学
【英語紙芝居の様子】

<生徒作製の紙芝居> |

<文化祭のステージでの発表の様子> |

<教室での発表の様子> |

<教室での発表の様子> |
(4)参加申込 別紙参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入してFAXでお申し込みください。
参加申込書はこちらからダウンロードできます。↓
http://www.nps.ed.jp/seisho-hs/annai/index.html
FAX番号:0745-62-6662
申込締切:11月6日(金曜日)
※次の(1)、(2)の内容を記入の上、はがきでお申し込みいただいてもかまいません。
(1)参加児童、保護者等の氏名
(2)小学校名、学年(保護者等のみの参加の場合もご記入ください。)
[児童のみの参加の場合、連絡先電話番号もご記入ください。]
〒639-2200 奈良県御所市525番地 奈良県立青翔中学校宛
11月6日(金曜日)までに投函してください。
(5)その他
児童のみの参加も可能ですが、「青翔中学校について」、「入学者選抜について」の各説明は保護者向けとなっています。
安全面から、できるだけ保護者等も一緒にご参加ください。児童のみの参加の場合は、参加申込書に連絡先電話番号の記入をお願いします。
青翔高等学校説明会と、同時並行で実施しますので、中学生もたくさん来校しています。
当日は上履きと靴袋をご持参ください。
お越しの際、お車の利用は大変混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用ください。
○11月14日(土曜日)当日の午前6時30分現在で奈良県北西部地域内の市町村において何らかの気象警報発表中の場合は中止しますのでご注意ください。
※お問合せ先
奈良県立青翔中学校・高等学校
〒639-2200 奈良県御所市525番地
電話番号:0745-62-3951
※青翔中学校に関する様々な情報は、次のWebページからもご覧いただけます。
青翔中学校Webページ http://www.nps.ed.jp/seisho-hs/junior/index.html
学校教育課県立中学校Webページ http://www.pref.nara.jp/31768.htm
奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第8期の第3回ワークショップが、平成27年10月10日(土曜日)に県立教育研究所で行われました。
リクルーターの河合町立河合第三小学校、竹田有希先生がワークショップの活動を報告します。
***************************************************
第3回ワークショップを振り返って
10月10日(土曜日)に第3回ワークショップが行われ、受講生は初めての模擬授業に取り組みました。小学校教員志望班の教材は2・4・6年生の国語科「詩」でした。各班3グループに分かれ、それぞれ1学年ずつを担当して模擬授業を行いました。
当日の朝は、時間いっぱいまで学習指導案を読み返したり話し合ったりする姿が見られ、それぞれのグループが、この日までにじっくり時間をかけて授業案を練り、各学年の発達段階に合わせて教具や掲示物を考え、準備してきたということがうかがえました。
そうして始まった模擬授業。わずか15分という限られた時間の中で、それぞれのグループの代表1名が授業をしました。授業の後、受講生同士で、良かった点や改善点を付箋に書き、書いた内容によって分類して模造紙に貼っていきました。分類し整理することで課題が明らかになり、授業者だけではなく受講生全員にとって学びの多い模擬授業だったように思います。
アドバイザーの先生やリクルーターからの指導助言では、
学年に応じた板書の文字の大きさを考えたほうが良い。
教室の大きさを想定した声を出す必要がある。
指示が分かりにくい。短く簡潔な指示を出す必要がある。
詩というものは児童に音読させる場面がたくさんあったほうが良い。
などが出され、受講生はメモを取りながらその一つ一つを自分のものにしようと熱心に聞いていました。
初めての模擬授業で、緊張しつつ真剣に取り組む受講生の姿を見て、私たちリクルーターも、日頃子どもたちの前に立つ自分たちの姿と重ね合わせ、客観的な視点から自分の授業を見直す良い機会となりました。アドバイザーの先生が受講生に向けておっしゃった助言の中に、「授業を受ける受講生は、子どもになりきって授業に参加しなければならない」という言葉がありました。子どもの視点に立った授業づくりをするには、子どもの視点に立たないと分からないというお話を聞き、私たちも「子どもの視点」を常に意識して授業に臨まなければならないと改めて感じました。
今回で3回目のワークショップでしたが、終わった後は毎回「月曜日からまたがんばろう」と決意を新たに、現場に戻ることができます。この取組が私たちにとっても良い学びの場となっています。
次の模擬授業はいよいよ個人での取組となります。今回いただいた指導やアドバイスをもとに、自分自身の課題が解決できるよう研究を重ねていってほしいと思います。しかしながら、模擬授業は同時に班のメンバーとのせめぎ合いでもあります。ライバルであり同じ夢をもつ良き仲間とともにステップアップできることを願っています。

<受講生による模擬授業の様子> |

<模擬授業後の話し合いの様子> |
今年度は、奈良県内の各市町村、各学校等の自慢の給食を紹介します。地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れた献立です。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、是非お試しください。
***************************************************
今月の献立★
*豚肉のごま塩麹から揚げ
*ゆずなます
*さけ香る豆乳かす汁
*柿
*黒米入りさつまいもごはん
*牛乳
レシピ★
画像をクリック→
|
 |
***************************************************
〔献立紹介〕
献立のテーマは「目で見ておいしい、香っておいしい、食べてみてもっとおいしい季節感たっぷりの献立」です。どの料理も地元の食材がアクセントとなり、宇陀市ならではの味を作り出しています。
例えば、豚肉のから揚げには、塩麹をもみこむことで厚切りのお肉であってもやわらかい食感を楽しむことができます。また、米粉とごまをつけて揚げているので衣が分厚くなることがない上に、香ばしさもあります。
なますは、ゆずの皮を細かく刻んで香りを移すことでさわやかな味に変化します。豆乳かす汁は、豆乳の臭みをみそが消してくれているのですが、そこに酒かすを少し加えることでまろやかな味に仕上がります。
【1】「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定
<県立教育研究所>
奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後6時~午後7時)の中で、午後6時40分~45分頃に放送します。
○11月11日(水曜日) 「みんなあつまれ! いのちかがやき フェスティバル」
「みんなあつまれ! いのちかがやき フェスティバル」実行委員会
○11月18日(水曜日) 「奈良発!未来を創造するグローバル・リーダー育成プログラム」
県立畝傍高等学校
○11月25日(水曜日) 「奈良県産業教育フェア」
奈良県教育委員会・奈良県産業教育振興会
過去の放送分は、こちらの Webページでご覧いただけます。
※お問い合わせ先
県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係
TEL0744-33-8907 FAX0744-33-8909
【2】平成27年度「奈良県教育の日」及び「奈良県教育週間」について
<企画管理室>
県教育委員会では、教育に対する県民の意識や関心を高めるとともに、家庭、地域社会及び学校が一層連携を深め、奈良県教育の充実と発展を図ることを目的に、毎年11月1日を「奈良県教育の日」と定め、その日からの1週間を「奈良県教育週間」としています。
この期間中、県教育委員会、各市町村教育委員会、各学校及び教育関連団体が「奈良県教育の日」の趣旨を踏まえて、関連行事や授業公開等の取組を行います。
取組の詳細は、こちらのWebページでご覧いただけます。
※お問い合わせ先
企画管理室 企画法令係
TEL0742-27-9830
【3】「奈良県文化財の日」及び「文化財保護強調週間」について
<文化財保存課>
多くの文化財を有する奈良県では、平成21年より11月3日を「奈良県文化財の日」と定め、文化財を保存して次世代に継承することはもとより、積極的に公開・活用を行うように努め、県民の方々に、より文化財を身近に知っていただく機会としています。
また、毎年11月1日~7日は、全国的に「文化財保護強調週間」(文化庁、今年で62回目)として、広く国民の文化財に対する理解と関心を深め、文化財保護の一層の協力を得ることを目的に、様々な取組が展開されています。
※お問い合わせ先
文化財保存課 総務企画係
TEL0742-27-9864
2015年10月30日 第62回日本学書展について
2015年10月28日
2015年10月27日
2015年10月26日
2015年10月26日
2015年10月26日 平成27年度全国中学校体育大会優勝選手・監督等の副知事、教育長表敬訪問について
2015年10月26日 ボクシング世界ジュニア・インターハイ・国体代表選手等の表敬訪問について
2015年10月23日
2015年10月23日 平成27年度学校給食に関する文部科学大臣表彰について
2015年10月22日 平成28年度奈良県公立高等学校入学者募集人員
2015年10月21日
2015年10月20日 平成27年度識字合同学習会(第14回ふれあい広場)を開催します。〔入場無料、申込み不要〕
2015年10月20日
2015年10月19日 旧奈良工業高等学校の土壌汚染対策調査について
2015年10月16日
2015年10月15日
2015年10月15日
2015年10月09日
2015年10月09日
2015年10月08日 入札公告(史跡・名勝飛鳥京跡苑池(石造物付近)地形模型製作委託業務
2015年10月07日 教育長表敬訪問
取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。また、メールマガジンの読者登録もしていただければ幸いです。
「奈良県先生応援サイト」はこちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。
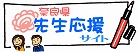
※Q&Aのページはパスワードが必要です。
このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。
「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。
http://www.mag2.com/wmag/
「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、 こちらへ。
※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。
※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。
http://www.pref.nara.jp/30523.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室
〒630-8502 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-22-1101(代表) 内線 5352
0742-27-9830(直通)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
|