「E-夢 はっしん!」
平成28年12月1日(木曜日)
≪第 258 号≫
■このメールマガジンを保存いただく方法は、 こちらをご覧ください。
■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。
■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、 こちらをご覧ください。
発行:奈良県教育委員会事務局 教育政策推進室
「行ってきたよ」
奈良県教育委員会事務局
学校教育課長 深田 展巧
私は、25年間、中学校で数学の教員をしてきた。
中学校3年の夏休み前にもなると担任するクラスの生徒から、よく進路の相談を受ける。卒業後の進路を考え始めるときには、子どもの思いと保護者の思いが同じ方向を向いていないことがよくある。家庭での十分な話し合いが大切である。
これは、私が担任をした女子生徒との出来事である。
保護者の思いは普通科への進学、本人の思いは農業科への進学であった。「動物が大好き」という理由だった。保護者の思いを聞いた私は、思い悩んだ結果、保護者の思いに立ち、「普通科に行って、高校でもう一度、将来を考えてみては」等、彼女といろいろ話をした。
ある時、私は「一度、学校を見に行ってきたら」と声をかけた。すると彼女は「行ってきたよ。高校の先生に案内してもらった。よかったよ」とニコニコしながら答えた。彼女はすでに、自らその農業科のある高校の見学に行っていたのだ。
私は、その時『はっ』とした。どうして彼女のこれほどまでの強い思いに気づかなかったのか。
彼女は希望通り農業科畜産コースに進学した。
次の年、私はPTAの高校見学会に同行し、彼女の高校を訪問した。彼女は、私を見つけるなり走り寄ってきた。その目には涙があふれていた。
高校では彼女は、先生方の熱心なご指導の下、近鉄百貨店橿原店で開催された奈良県産業教育フェアでの畜産のPR等を行ったり、また、近畿や全国の産業教育フェアでも酪農家の体験を発表するなど大活躍していた。
ご家族の方も娘の頑張りを応援されていた。
高校卒業後、彼女は八ヶ岳実践農業大学校に進学し、人工授精師の資格も取った。奈良県に帰ってからは植村牧場に勤め、現在は五條の酪農家の方と結婚し、2児の母として酪農を営んでいる。
果てしない大空と 広い大地のその中で
いつの日か幸せを 自分の腕でつかむよう
歩き出そう明日の日に・・・
【大空と大地の中で 松山千春】
【1】平成28年度奈良県教育委員会選奨について
<企画管理室>
奈良県教育委員会選奨は、昭和24年度に創設され、今回で68回目を迎える栄えある表彰制度です。学校教育分野、社会教育、保健体育、文化財保護などの分野において、長年にわたり尽力され、優れた業績を残された方々や団体を表彰しています。今年度は、下記の15名(男13名、女2名)の方々が受賞されました。
<氏名> <所属> <主な功績>
阪本 さゆり 奈良市立三碓小学校長 学校教育推進
上村 晴彦 奈良市立朱雀小学校長 生徒指導
近藤 憲司 大和郡山市立片桐小学校長 保健体育
山口 德夫 橿原市立畝傍東小学校長 学校経営
中村 衛 上牧町立上牧小学校長 人権教育
三宅 薫 大和郡山市立郡山南中学校長 学校教育推進
松長 一樹 県立奈良朱雀高等学校長 生徒指導
阪部 清 県立奈良情報商業高等学校長 学校経営、進路指導
柴田 秀治 県立大和広陵高等学校長 保健体育
藤田 和義 県立高田高等学校長 人権教育
山本 肇一 県立五條高等学校長 学校経営、教育行政、教育相談
細川 憲次 県立二階堂養護学校長 特別支援教育
梅田 真寿美 奈良市教育委員会事務局学校教育部長 学習指導
木下 亘 県立橿原考古学研究所附属博物館副館長 埋蔵文化財の保護
幹田 秀雄 文化財保存事務所法隆寺出張所主任 文化財建造物の保存修理
授与式は、11月24日(木曜日)に「ホテルリガーレ春日野」(奈良市法蓮町)において、来賓に松谷副知事を迎え開催しました。
※お問い合わせ先
企画管理室 秘書人事係
TEL 0742-27-9816
【2】平成28年度教育者表彰について
<教職員課>
教育者表彰は、学校教育の振興に関し、特に功績顕著な教育者の功労をたたえるという趣旨で行われている文部科学大臣表彰です。昭和34年から毎年実施されており、今年は県内から次の4名の方々が表彰されました。
奈良県教育委員会事務局 荒木 保幸 教育次長 (磯城郡田原本町在住)
奈良県公立高等学校長の経験を生かし、魅力と特色のある学校づくりに向けて、県内の学校教育の充実、発展に寄与されています。
広陵町立真美ヶ丘中学校 植村 佳央 校長 (北葛城郡広陵町在住)
奈良県中学校長会会長として活躍し、校長同士の情報・意見交換の機会を充実させるなど、中学校教育の一層の発展に成果をあげておられます。
王寺町立王寺南小学校 山田 均 校長 (北葛城郡王寺町在住)
奈良県小学校長会会長として、課題が山積する学校現場において全県的な立場から指導・助言をするなど、本県小学校教育を牽引し成果をあげておられます。
エンゼル幼稚園 前田 良一 園長 (大阪市在住)
奈良県私立幼稚園連合会会長、全日本私立幼稚園連合会理事等を務められ、奈良県のみならず全国の幼児教育振興に寄与されています。
※お問い合わせ先
教職員課 定数管理係
TEL 0742-27-9805
【3】高校生から未来へ、夢の発信~第25回奈良県産業教育フェアを開催しました~
<学校教育課>
高校生等による産業教育に関する成果等の総合的な発表の場である「奈良県産業教育フェア」を、イオンモール橿原で11月19日(土曜日)に開催しました。多くの方々にご理解とご支援をいただくことで職業に関する学科に学ぶ生徒の励みとし、高等学校における産業教育のより一層の活性化を図るとともに、小・中学生の進路選択にも役立てる目的で実施しています。
※お問い合わせ先
学校教育課 学事係・高校教育係
TEL 0742-27-9851
【4】平成28年度地域文化功労者表彰について
<文化財保存課>
平成28年12月2日(金曜日)、文部科学省において、平成28年度地域文化功労者表彰が行われます。これは、「永年その業務に精励し又は献身的な努力を払い、地域における芸術文化の振興又は文化財の保護に貢献した個人を『地域文化功労者』として表彰」するものです。
奈良県からは、永年にわたり、奈良県文化財保護指導委員等を努め、地域文化の振興に貢献したことにより、次の方が表彰されることになりました。
矢野 達生 奈良県文化財保護指導委員
※お問い合わせ先
文化財保存課 総務企画係
TEL 0742-27-9864
【5】国の文化財指定の答申について
<文化財保存課>
平成28年11月18日(金曜日)に国の文化審議会文化財分科会において、国の文化財指定の答申がありました。奈良県に関係するものは以下の2件です。
史跡の新指定
1.名 称 箸墓古墳周濠
2.所在地 桜井市大字箸中
3.面 積 指定地:15,055.25 平方メートル
史跡の追加指定
1.名 称 与楽古墳群
与楽鑵子塚古墳
与楽カンジョ古墳
寺崎白壁塚古墳
2.所在地 高市郡高取町大字与楽
3.面 積 既指定地:15,588.00 平方メートル 追加指定地:3,061.00 平方メートル
詳しくは こちら
※ お問い合わせ先
文化財保存課 記念物・埋蔵文化財係
TEL 0742-27-9866
<文化財保存課>
平成28年11月18日(金曜日)に開催された国の文化審議会において、奈良県内では、奈良市に所在する4件(奈良町にぎわいの家主屋ほか3件)の建造物を登録有形文化財(建造物)として登録するよう答申がなされました。
詳しくは こちら
※ お問い合わせ先
文化財保存課 建造物係
TEL 0742-27-9865
曽爾中学校は、総合学習の時間を「ふるさとタイム」として、郷土学習を行っておられます。現在は、「ふるさと自然」「ふるさと物産」「ふるさと芸能」「ふるさと発信」の4つのグループに分けて実施されています。その中から、「ふるさと芸能」の学習を紹介していただきました。
***********************************************
曽爾の獅子舞を受け継ぐ
曽爾村立曽爾中学校
校長 山邊 尚治
曽爾中学校では、「ふるさとタイム」(総合的な学習の時間:週2時限)において、村の伝統芸能の「曽爾の獅子舞」や「曽爾の自然を活用した物づくり」そして「花づくり」など、コースに分かれて村内指導者による学習を行っています。中でも村の門僕(かどふさ)神社、例祭で奉納される「曽爾の獅子舞」(奈良県無形民俗文化財に指定)を習う「ふるさと芸能」は、村の奉舞会の方々から獅子舞の歴史や人々の思いについて話を聞くとともに、舞手・鳴り物の担当者を決め、村に300年前から伝わる伝統の舞に取り組んでいます。今年も10月9日の秋祭りで多くの村の人や観光客の見守る中、練習してきた舞を演じました。
村の若者は、進学や就職でそのほとんどが、やがて村を離れていきます。中には高校進学で村を離れる者もいます。そんな中、村伝統の獅子舞に触れ、その身で感じるこの体験は貴重なものです。村祭りで生徒たちの舞を見ていた村の人がこんなことを言います。
「この子らも、やがて村を離れるやろけど、獅子舞をやったことが、少しでも残ったらいい。そして、できたら、またいつか村へ戻ってきてくれたら・・・」
10月16日には、奈良公園の「奈良県猿沢イン」で行われた海外観光客への催しで曽爾村をアピールすべく、多くの観光客の前で獅子舞を披露しました。
「曽爾の伝統」は、こうした活動を通して、生徒たちの中に息づいています。

<地元の方に学ぶ練習の様子> |

<門撲神社の秋祭り> |

<「猿沢イン」での催しの様子> |
奈良TIME2016
「伝統とは」ずっと続いてきたもので これからもつないでいくもの
県立大宇陀高等学校
「大宇陀の魂を感じ、誇りに思った」「卒業生が母校と地域への愛着を強く感じていた」
3つのテーマのもとで、奈良TIMEを通して学んだことです。
今年度は、3年生が学校のある宇陀松山地区の町歩きをしました。地域の特徴や歴史を知ったり、卒業生や地域との交流体験したりするなど、卒業後の自分の姿を考える機会にしています。自信と誇りをもって社会で活躍をしてほしいというねらいで実施しています。
開講1時間目の様子です。学習の内容と計画を説明し、グループで話し合いをしています。
第1弾 「大宇陀の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば『新発見』!」
ふだんはゆっくりと歩くことがない学校の周辺や観光スポットを探索しました。施設を訪れ、話を聞きました。「行ってみたい!」と思えるような紹介文を書き、写真を撮って地図を作りました。
<特産物やお店の特徴を聞きました> <観光マップを作成しました>
(うだ・アニマルパークに展示中)
第2弾 「豊けしここに宇陀の黒豆」
黒豆が宇陀の特産であることを知り、畑作りをしました。黒豆と一緒にサツマイモも植えて、大宇陀こども園の園児と芋掘り交流をしました。
<畝作り> <芋掘り交流>
第3弾「三年(みとせ)を集い進む希望の八角塔」
14名の卒業生へのインタビューを実施し、思い出や武勇伝、後輩たちへ期待することを聞きました。卒業生だからこそ言える、熱いメッセージでした。
<文化祭で全校生徒に向けて発表> <卒業生へのインタビューの様子>
<学校教育課>
高校入試インフォメーションのコーナーでは、中学生の皆さんや保護者の方々に、平成29年度入試についての情報を紹介しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は、平成29年度高校入試に関する情報をQ&A形式でお届けします。
【Q1】今年2月に実施された特色選抜の問題は、どうすれば入手できますか。
→A
特色選抜では、各高校は、学力検査(県教育委員会作成の問題、原則として3教科)を実施するとともに、学校独自検査(独自問題、作文・小論文等)、面接、実技検査の中から1種類以上の検査を実施します。
学力検査の問題については、こちらをご覧ください。
独自問題や作文・小論文、実技検査(一部は公開しておりません。)については、当該高校の事務室や県庁東棟1階にあります県政情報センターで、閲覧したり、有料で写しの交付を受けたりできます。
なお、面接や口頭試問については、公表していません。
【Q2】特色選抜では、「自己アピール文」が必要と聞きましたが、どのようなものですか。
→A
「自己アピール文」は、特色選抜において面接を実施する高校及び大和中央高校定時制課程(A選抜、B選抜)に出願する際に必要な書類です。
「自己アピール文」には、志願する理由、中学校や地域での活動、資格の取得等について、特にアピールしたいことを記入してください。特色選抜や大和中央高校定時制課程の選抜の面接では、この「自己アピール文」を資料として面接を実施します。ただし、「自己アピール文」そのものを点数化することはありません。
なお、「自己アピール文」は、志願者本人が黒色のボールペンで記入するか、鉛筆で記入してから、コピーしたものを提出してください。
※平成29年度入学者選抜の日程、入学者選抜実施要項及び入学者選抜概要は、学校教育課のWebページ「高校入試」に掲載しています。そのほかに、高校進学に関して次のような情報も掲載していますので、活用してください。
● 公立高等学校・特別支援学校紹介
学校別に学校の所在地や特色、行事、部活動、進路状況、制服など、写真入りで様々な情報を紹介しています。
● 平成29年度奈良県立高等学校入学者選抜に関するQ&A
※ 担当
学校教育課 学事係
TEL 0742-27-9851
奈良県ディア・ティーチャー・プログラムのワークショップを開催しました
奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第9期の第4回ワークショップが、平成28年11月13日(日曜日)に県立野外活動センターで行われました。
受講生の長沢有規さんと近重貴久子さんが、活動を振り返って報告します。
***********************************************
野外活動研修で学んだこと
今回の野外活動で、私は「自然観察とクラフト」と「リスクマネジメントと森林教育」の活動に参加し、学びました。
「自然観察とクラフト」では、木の名前や特徴、木肌や葉からの見分け方などを教えていただきました。今までは木は木としか思っていなかったものも、特徴等を知り見分けができるようになると、「木をみる」ということがとても面白いことなのだと感じることができるようになりました。また子どもの立場にも立って学びましたが、今まで知らなかったこと、新しいことを学ぶということは楽しいことであり、木に関して興味をもち、より学びたいと感じました。木に限らずほかの教科指導においても分かりやすく楽しいと思わせることで、子どもの興味・関心を引き出すことができるのではないかと実感しました。また担当の先生が私たちに、よりわかりやすく伝えようとしてくださっている様子から、子どもに聞かせる工夫、まとめる工夫等も学ばせていただきました。
「リスクマネジメントと森林教育」では、班に分かれて野外活動センター内を探索し、危険だと思うところを探し、その解決策を考えました。そのあと、班ごとの発表を行いました。班で意見をまとめるときでも様々な意見が出てきていたのに、班ごとの発表ではそれ以上の意見が出てきていたので、たくさんの目で見ることがより良いリスクマネジメントにつながるのだと思いました。しかし、実際の現場ではたくさんの目で見ることは難しいので、個々がしっかりとリスクを予見することが重要になります。また、教員という大人の立場だけでは見つけられないリスクもたくさんあると思うので、子どもの立場に立って考えるのも大切だと感じました。
今回野外活動リーダーを経験し、校外学習における教員の果たすべき役割の大変さを垣間見ることができたのではないかと思います。今回は対象が大学生なので危険な行動等はありませんでしたが、小学生となるとたくさんのリスクが出てきます。そのようなことも踏まえて、綿密な計画を練り、周りを見ることができるようにならなければならないと思いました。
第9期受講生 C班 長沢有規
**********************************************
野外活動を通して学び感じたこと
野外活動では、様々な自然と触れ合い、木や花の魅力を感じたり、動植物の危険性を学んだりすることができました。また、集団活動を進めていく上で、協調性や人間関係を築いていくことが大切だということを改めて考えることができました。
リスクマネジメントについての活動では、コミュニケーションを取りながら一つのものを共に創り上げることで、達成感や成就感を共に感じることができ、それによって仲間との関係が深まったように感じました。
ハイキングコースの自然観察では、仲間と一緒に楽しく散策することで草木の知識などが印象深くインプットされ、記憶に強く残ることがわかりました。直接体験を通して、自然と人との共存を感じたり、人とのつながりを大切にして共に活動を楽しんだり、散策から生まれた疑問について意欲的に調べたり知ろうとする気持ちが育まれたりすることを体感しました。
さらに、活動を深めるために必要なことは、ふだんから児童との信頼関係を築き、学級経営を大切に進めておくことだと学びました。危険予測をするにあたって、児童の実態を知っておくことで事前に対策を考えることができます。集まるときと話を聞くときの合図、姿勢、約束などのふだんからの学級規律がしっかりと徹底できていれば、今回のような野外活動でも生かされスムーズに活動できることを学びました。事前の実地調査を行うときには画像や動画を撮り、先の見通しがもてるような配慮をすること、雨の日の危険予測を行うことも重要だと学びました。
今回、野外活動リーダーをさせていただいたおかげで、指導者側の立場を身をもって感じることができました。特に、全体の流れをつかみ、指示を出していくことやリーダー同士の共通理解を図ることの難しさを感じました。自分が教員になったとき、「今は何をすべき時間なのか」、「次の指示は何なのか」を明確に伝えることで児童が騒がしくなったり集団から離れたりすることがなくなるのだと実感しました。
以上のように、今回の活動で様々なことに気付くことができました。このような機会を設けてくださり、ご指導をいただいたセンターの皆さんやスタッフの方々に感謝いたします。
第9期受講生 H班 近重貴久子
<自然観察の様子> <リスクマネジメントについての話合い>
今年度は、奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした学校給食の献立をご紹介します。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。
***********************************************
★今月の献立★
*そぼろどんぶり
*昆布和え
*大根のみそ汁
*みたらしだんご
*牛乳
★レシピ★
画像をクリック→
|
 |
***********************************************
〔献立紹介〕
奈良県産の食材を購入することはなかなか困難ですが、冬場のほうれん草、青ねぎは定期的に購入できています。また、大根は学校農園で栽培、収穫されたものを使いました。生徒からリクエストメニューを募集したところ、デザートに「みたらし団子」のリクエストがありました。奈良県産の米粉の団子を使用し、みたらしのたれをかけて提供したところ、「おいしい」と好評でした。
【1】「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定
<県立教育研究所>
奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後6時~午後7時)の中で、午後6時35分~40分頃に放送します。
○12月7日 (水曜日) 『感性を育む芸術系学科での学び』
県立高円高等学校
○12月14日(水曜日) 『奈情商たまつえストア』
県立奈良情報商業高等学校
○12月21日(水曜日) 『地域とのつながりを通した学び』
県立吉野高等学校
■過去の放送分はこちらの Webページでご覧いただけます。
※お問い合わせ先
県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係
TEL 0744-33-8907
FAX 0744-33-8909
2016年11月25日 「地域と共にある学校づくり」の取組ニュースを更新しました
2016年11月25日
2016年11月22日 平成28年度教育者表彰について
2016年11月22日
2016年11月18日
2016年11月18日
2016年11月18日「地域と共にある学校づくり」の取組ニュースを更新しました
2016年11月17日
2016年11月16日
2016年11月14日 「地域と共にある学校づくり」の取組ニュースを更新しました
2016年11月11日 第25回奈良県産業教育フェア
2016年11月11日 親子ふれあい運動遊び教室の開催について
2016年11月10日奈良県教育委員会選奨の被表彰者の決定
2016年11月07日
2016年11月02日
2016年11月01日
取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。また、メールマガジンの読者登録もしていただければ幸いです。
「奈良県先生応援サイト」は こちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。
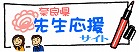
※Q&Aのページはパスワードが必要です。
◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。
「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。
http://www.mag2.com/wmag/
◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、 こちらへ。
※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。
※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
◎当マガジンの登録及び解除は、 こちらへ。
http://www.pref.nara.jp/30523.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
発行:奈良県教育委員会事務局 教育政策推進室
〒630-8502 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-22-1101(代表) 内線 5352
0742-27-9830(直通)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
|