「E-夢 はっしん!」
■このメールマガジンを保存いただく方法は、
こちらをご覧ください。
■このメールマガジンは「文字サイズ 中」でデザインしています。
■レイアウトが崩れて見える場合や、文字サイズを変更したい場合は、
こちらをご覧ください。
発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室
部活動をとおして
奈良県教育委員会事務局
保健体育課長 栢木 正樹
先日、16年前に高校で顧問をしていたバレーボール部の集まりに出かけ、懐かしい面々と再会しました。私も含め、寄る年波には勝てませんが、笑顔はあの頃と変わらず、皆とても元気で、選手時代の話を昨日のことのように自慢げに話していました。また、幼児から中学生までの娘や息子も十数人来ていたので、とても賑やかな会となりました。
私は久しぶりでしたが、部員たちは機会があれば集まったり、連絡を取り合ったりしていたようです。今年、メンバーの一人の家族に急な不幸が起こり、当然ですが、本人はとても悲しみ、落ち込んだそうです。そんな時、このメンバーが真っ先に駆けつけ、声をかけ励ましてくれたことが、本当にありがたかったという話を聞きました。
高校時代からとても仲のいいメンバーでしたが、楽しい時だけでなく、辛い時にも支え合える関係が今も続いていたのです。スポーツを通して培われた絆の強さを感じ、スポーツの力を再認識しました。
部活動は学習指導要領で「スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するもの…」と示されています。部活動の果たす役割は、学校生活はもちろん、家庭生活や卒業後の人生にとっても大変大きいと思われます。
今年の3月に、スポーツ庁が「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定しました。中身としては、○部活動の適切な運営のために、県や市町村教育委員会等が基本方針を策定することや、学校が部活動の活動計画の公表等を行うこと。○適切な休養日等として、週当たり2日以上の休養日、平日2時間、休業日3時間程度の活動時間を設定すること。○生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備を行うこと等、県、市町村教育委員会、学校等が、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築することを目指しています。
現在、奈良県・県教育委員会でも、今回のガイドラインに基づいて、運動部活動の在り方に関する基本方針を策定しているところです。平成29年度の本県の運動部活動の加入率は、中学校が60.9%、高等学校が41%となっていますが、今後、運動部活動の指導・運営に係る体制が整備され、より多くの生徒が参加することを期待しています。生徒が、運動部活動を通して、体力や技能の向上とともに、人との絆を深め、生涯にわたって豊かなスポーツライフを過ごすことができるよう、取り組んでいきたいと考えています。
スポーツを通して友情を育んだ仲間たちと、また10年後、20年後に笑顔で集える日を楽しみにしています。
「平成29年度研究報告」をWebに公開しています
<教育研究所>
平成29年度の教育研究所におけるプロジェクト研究・個人研究の成果を「研究報告」として、教育研究所のWebページにて公開しています。
くわしくは こちら
※お問い合わせ先 県立教育研究所 研究開発部 教科教育係 TEL 0744-33-8903 FAX 0744-33-8909
県立二階堂高等学校で実施されている「地域活性化に向けた課題研究」について紹介します。
***************************************************
地域活性化に向けた課題研究
~「フィールドワーク」の実施~
県立二階堂高等学校
県立二階堂高等学校(岡本雅至校長)は、平成29年度より文部科学省委託事業「実社会との接点を重視した課題解決型学習プログラムに係る実践研究」の研究校として、地域活性化に向けた課題研究に取り組んでいます。
この研究では、天理市を中心とした地域について、県内5大学(奈良県立大学、奈良女子大学、天理大学、帝塚山大学、奈良佐保短期大学)の先生方の指導を受けながら自ら課題を見つけ、仲間と協働して解決するための提言を行います。
この度、2年生が各地域を実際に訪問してニーズを探り、課題を発見するための第1回のフィールドワークオリエンテーションを4月25日(水曜日)に、4月27日(金曜日)と5月9日(水曜日)の2回、フィールドワークを実施しました。
フィールドワークオリエンテーションでは、各クラスごとに大学の先生方からフィールドワークの目的や内容について先生方の講義を受け、活発な話し合いを行いました。
フィールドワークでは、各クラスが天理市内中心部、天理市立北中学校区域、天理市立南中学校区域、天理市立西中学校区域、天理市立福住中学校区域の5地域を訪問しました。生徒達は、地域の方々に自分たちで考えた質問をしてみたり、地域の様子を撮影したりするなどグループごとに様々な活動を行いました。
生徒達からは、「実際に行ってみて見所がたくさんある、すてきな町だということに気付いた。」「地域のみなさんの話を聞いて、ただ見たり調べたりしているだけでは分からなかったことにたくさん気付くことができた。」等の感想が寄せられました。
本校生徒にとっても、地域への貢献の在り方を考えるとともに、学校周辺の地域に対しての愛着を深めるよい機会となるため、今後もこのような活動を、より推進したいと考えています。
今後の予定
「二階堂フェスタ」 (中間発表会) 11月10日(土曜日)天理駅前広場等
「キャリアデザイン科発表会」(最終発表会) 2月 9日(土曜日)天理市民会館

フィールドワークオリエンテーション(講義)

フィールドワークオリエンテーション(話し合い学習)

フィールドワーク
今月から【高校入試インフォメーション】をスタートし、中学生の皆さんや保護者の方々に、平成31年度入試についての情報を紹介していきます。
今月は、今年の2月、3月に実施された平成30年度入試を紹介します。
***************************************************
平成30年度入試を振り返って
1 選抜の実施について
(1) 特色選抜
全日制課程の専門学科、総合学科と普通科の第1学年から定員を定めて募集するコースで実施する選抜です。今年度は、公立高校23校で実施しました。
(2) 一般選抜
一般選抜において定員を定めて募集する学科(コース)及び特色選抜で合格者数が定員に満たなかった学科(コース)で実施する選抜です。今年度は、公立高校全日制課程27校、定時制課程5校で実施しました。
(3) 二次募集
特色選抜及び一般選抜等で定員に満たなかったすべての学科(コース)で実施する選抜です。今年度は、県立高校全日制課程9校、定時制課程5校で実施しました。
(4) その他の選抜
県立大和中央高校の定時制課程では、Ⅰ部(午前の部)、Ⅱ部(昼間の部)、Ⅲ部(夜間の部)ともA選抜、B選抜を実施しました。また、帰国生徒等を対象とした特例措置、県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜を実施しました。
実施校や出願者数については、こちらをご覧ください。
2 学力検査結果から
各教科とも基礎的・基本的な問題の正答率はおおむね高く、中学校での学びの成果が現れています。記述式の問題においては、論理性に欠ける解答や、問いの趣旨を十分理解できていない解答が多く見受けられました。文章や資料を読み取る力や、自らの考えを論理的に表現する力の向上を目指しましょう。また、具体的な事象を調べることを通して学習への興味・関心を高めたり、日常生活と関連付けたりしながら、学ぶことの意義や有用性を実感して学習に取り組まれることを期待しています。
学力検査問題については、こちらをご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※お問い合わせ先 学校教育課 学事係 TEL 0742-27-9851
※高校入試に関する情報は、次のページをご覧ください。
県立青翔高等学校の小山愛桂さんは、第39回「少年の主張」奈良県大会で優勝され、全国大会に出場されました。小山さんの大会に出場しての思いを綴っていただきました。
なお、今年度の第40回「少年の主張」の募集が今日から始まりました。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。
***************************************************
「挑戦」
県立青翔高等学校
1年 小山 愛桂
「百聞は一見に如かず」という言葉があります。
「少年の主張」全国大会に行って感じたことは、出場者の発表レベルがとても高いということです。
「少年の主張」は、中学生の弁論大会のようなものですが、皆さん、聞き取りやすく分かりやすい話し方をされており、たいへん勉強になりました。
奈良県大会では、発表原稿を持たずに舞台に上がりました。本番前まで思いもよらなかったことでしたが、自然とそうしたのです。
自分は本番に強いと思っています。それは、両親をはじめ、親戚の方々や日頃お世話になっている先生方、その他関わってくださった多くの人々のおかげです。なぜなら、多くの人が私に与えてくれたものを背負って立つのだと考えるから、強くなれるのです。さらに、失敗しても支えてもらえるから、「何度でも立ち上がろう」という不屈のチャレンジ精神があふれてくるのです。
挑戦するということは、時には茨の道を行くということです。そんな時こそ人々への感謝を忘れずに進みたいと思います。そして、将来、職に就いたら、発表作文にも書いたように、真摯に誠実にその務めを果たし、社会貢献していきたいと思います。
今のところ、英語力を生かせる仕事をしたいと考えています。そのために、英語の検定試験に取り組んでおり、英検2級に合格することができています。今後は、英検でさらに上を目指すのはもちろんのこと、TOEICなどにも挑戦し、将来の夢につなげていきたいと考えています。
最後に、「少年の主張」へ出場する機会をくださり、ご指導してくださった先生方、応援してくれた家族や友達に感謝します。そして、私が積極的に活動できる環境をつくってくださる数多くの方々に・・・。
第39回「少年の主張」入選原稿はこちら

第39回「少年の主張」奈良県大会表彰式 写真中央が小山さん

「少年の主張」奈良県大会の発表の様子
奈良県ディア・ティーチャー・プログラム第10期の第8回ワークショップが5月13日(日曜日)に、県立教育研究所で行われました。
リクルーターの広陵北小学校 奥田早苗先生が、ワークショップの活動を報告します。
*******************************************************
第8回ワークショップを振り返って
5月13日(日曜日)、第10期「奈良県ディア・ティーチャー・プログラム」の第8回ワークショップが行われました。今期のディア・ティーチャー・プログラムも終盤にさしかかり、受講生はこれまでのワークショップを通して得たことを生かし、自ら課題を設定して授業づくりを行っていました。
朝の学びタイムでは、リクルーターが普段どのような朝の会を行っているかを伝えました。内容は様々ですが、挨拶や、健康チェック、予定の確認、係からの連絡などは、子どもたちがその日一日を気持ちよく過ごすために必要不可欠なことだと感じました。また、「朝の1分間スピーチ」を取り入れている先生が多いようで、F班でもテーマを決めて受講生に行ってもらいました。実際にやってみると、1分間というのは短いようで意外に長く、1分間で伝えられることはたくさんあり、自らを発信し、仲間づくりのきっかけとなる貴重な時間であることがわかりました。
班別ワークショップでは模擬授業が行われ、受講生は、自らが選んだ学年、教科、単元で指導案を立て、授業に臨みました。F班の受講生は、積極的に英語科、道徳科の授業に挑戦しており、教科化を意識して、一層の授業力向上を目指す姿が素敵でした。また、今回は、それらの教科を扱う上で、基本的要素よりも専門的要素の難しさを感じる機会となりました。ねらいに即した指導を行うために、教師は本時のねらいを深く追求し、それに適した発問や活動を求める必要があります。基本的要素はもちろん、より専門的な知識や技術を追求し続けることが、受講生に限らず、教師の在り方だと感じました。
その後の講義では「生徒指導」について学びました。生徒指導とは、児童生徒自らの自己指導能力を育成するものであること、そして、そのためには教師と児童生徒との信頼関係が大切であることを教えていただきました。また、問題行動やいじめ問題にも触れていただき、それらは教師が意図的、計画的に未然防止していかなければならない課題であることを改めて感じました。
今回の講義で特に印象に残ったのが、講師の先生の「命を預かる」という言葉です。学校は児童生徒の命を預かる場所であり、だからこそ、その覚悟をもって、常に自身の知識や技術向上を追求し、授業や指導を行わなければなりません。教師が果たす役割や責任の重さを感じるとともに、子どもたちが「居場所」や「仲間」を見つけ、自ら成長していく過程をサポートできる"使命感"を忘れずにいたいと思いました。
第10期リクルーター 広陵北小学校 教諭 奥田 早苗

模擬授業の様子(1)

模擬授業の様子(2)
今年度は、奈良県内の地域の産物や行事食、旬の食材を取り入れるなどの工夫をした学校給食の献立をご紹介します。献立画像をクリックしていただくと、分量や調理の方法を見ることができます。ご家庭でも、ぜひお試しください。
*****************************************************
 |
★今月の献立★
*麦ごはん
*牛乳
*竹輪とかぼちゃの大和茶揚げ
*ひじきの炒め煮
*にゅうめん
*ふりかけ(ゆかり)
★レシピ★
←画像をクリック
|
*****************************************************
〔献立紹介〕
“大和茶”は、朝晩の温度差が大きい大和高原を中心に栽培されている奈良県の特産品です。毎年5月中頃には、香りも高くうまみの濃い美味しい新茶が出回ります。その大和茶を衣に混ぜ合わせて「大和茶揚げ」にしました。また、にゅうめんには、同じく奈良県の特産品である“なす”を使いました。なすは夏から秋にかけてが旬です。なすが苦手な子どもたちにも食べやすいよう、みそ味のにゅうめんにしています。
(1)「少年の主張」奈良県大会 発表者募集!
<くらし創造部 青少年・社会活動推進課>
毎年、東京都で開催される「少年の主張 全国大会」(独立行政法人国立青少年教育振興機構主催)に向けて、第40回
「少年の主張」奈良県大会~わたしの主張2018~を開催します。
○ 発表者募集
対象:奈良県内の中学生及びそれに相応する学籍、又は年齢にあるもの。
内容:次の(1)~(3)のいずれかの内容とし、思いや考えたこと、感銘を受けたことなどを感想として飾り気のない言葉でまとめたもので、400字詰原稿用紙4枚程度(1500字程度)で、発表時間5分程度(5分30秒未満)とする。
(1) 社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案など。
(2) 家庭、学校生活、社会(地域活動)及び身の回りや友達との関わりなど。
(3) テレビや新聞などで報道されている少年の問題行動、大人や社会の様々な出来事に対する意見や感想、提言など。
期間:平成30年6月1日(金曜日)~平成30年7月18日(水曜日)必着
審査:入賞(10点)、努力賞(60点)を選考
○ 第40回「少年の主張」奈良県大会~わたしの主張 2018~
日時:平成30年9月9日(日曜日)
13時30分~16時20分
場所:生駒市コミュニティセンター 文化ホール
生駒市元町1丁目6番12号
生駒セイセイビル1階(近鉄生駒駅下車すぐ)
発表者:入賞者10名
※最優秀賞発表を「少年の主張 全国大会」の発表候補として推薦します。
○ 詳細については、こちらをご覧ください。

昨年度の記念撮影の様子
※お問い合わせ先 くらし創造部青少年・社会活動推進課 活動支援係 TEL 0742-27-8615 FAX 0742-27-9574
(2)「なら教育リポート ~まなびだより~」今後の放送予定
<県立教育研究所>
奈良テレビ放送「ゆうドキッ!」(午後5時58分~6時55分)の中で、午後6時40分~45分頃に放送します。
○6月6日(水曜日) 「先生だから学ぶ ~教育セミナー2018~」
県立教育研究所
○6月13日(水曜日) 「学校の先生になりました!」
県立教育研究所
■過去の放送分は、こちらのWebページでご覧いただけます。
※お問い合わせ先 県立教育研究所 研究開発部 ICT教育係 TEL 0744-33-8907 FAX 0744-33-8909
2018年05月15日 障害のある子どもの就労支援に関する講演会の開催について
2018年05月15日 県指導主事のマネジメント能力向上事業(早稲田大学連携事業)の開催について
2018年05月08日 平成31年度奈良県・大和高田市公立学校教員採用候補者選考試験について
2018年05月02日 平成30年度奈良県公立高等学校入学者一般選抜学力検査の結果について
取り上げてほしい記事や、紹介してほしい学校の取組等がありましたら、本メールマガジンの下部にあります発行先までご連絡ください。
「奈良県先生応援サイト」は
こちらから。または「奈良県先生応援」で検索してください。
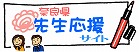
※Q&Aのページはパスワードが必要です。
◎このメールマガジンは、「まぐまぐ!」を利用して発行しています。
「ウィークリーまぐまぐ!」の配信が不要な場合は、こちらで解除できます。
http://www.mag2.com/wmag/
◎「E-夢 はっしん!」のバックナンバーは、
こちらへ。
◎本県の教育に関するご提言、ご意見は
こちらからお寄せください。
※お寄せいただいたご提言、ご意見は今後の教育行政の参考にさせていただきます。
※原則として、返信はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
◎当マガジンの登録及び解除は、
こちらへ。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┓
発行:奈良県教育委員会事務局 企画管理室
〒630-8502 奈良市登大路町30番地
TEL 0742-22-1101(代表)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛