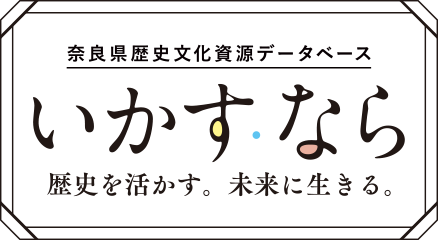歴史を活かす地域の取組
歴史を活かす地域の取組
- いかす・ならトップ
- 活かす
- 歴史を活かす地域の取組
- 番条のお大師さん

※山下氏提供
弘法大師のご縁日である4月21日に、番条の集落で毎年行われている風習です。80軒あまりの家々の玄関先に弘法大師像が開帳され、餅などが供えられます。人々は1軒1軒お参りをして巡ります。1年のうちこの日だけ、番条の集落に“四国八十八ヵ所”が現れます。
-
- 2017年12月

※郷土史編集者 加藤なほ氏提供
集落単位での八十八ヵ所巡り。
番条のお大師さんは、1830年代に始められたといわれています。弘法大師のご入定が835年ですから、その約千年後に当たります。当時、番条ではコレラが流行しており、その救いを求める意味で、ちょうど88軒あった集落の家々で弘法大師像をお祀りしました。四国八十八ヵ所になぞらえた風習は各地に見られますが、集落単位で八十八ヶ所を巡るというのは、番条独特の風習です。

※郷土史編集者 加藤なほ氏提供
4月21日には各地から多くの人が訪れ、番条は交流の拠点となります。
番条のお大師さんへの来訪者は、もともとは集落外から20~30人とこじんまりとした風習でしたが、最近では多くの人が訪れます。東京から来られる方や、郷土史研究の学生さんの姿も見られます。各家では、接待のための餅などを準備していますが、数が足りなくなるほどです。お大師さんのご縁日に多くの人が集い、番条が交流の拠点となることは非常に意義のあることですが、中にはマナー違反の行動も見受けられますので、配慮をお願いしたいですね。

※郷土史編集者 加藤なほ氏提供
地域の絆を深める「大師講」。
番条のお大師さんは弘法大師信仰の現れだといえますが、同じく大師信仰に由来するものとして、番条では、昔から毎月21日に「大師講」と呼ばれる集まりがあります。現在でも、集落の北と南に2つの「大師講」があり、北地区は大師堂に、南地区は当番(宿)の家に集まり、お念仏を上げます。昔は食事をしたり、講の人々で遊びに行ったりしたそうですが、現在ではお茶を飲みながら世間話をしています。「大師講」は、地域の人々のコミュケーションに欠かせないものであり、そのおかげで絆が深まっています。

※山下氏提供
独特の風習を守り続けるためには、さまざまな課題があります。
番条のお大師さんは、各家でそれぞれ大師像をお祀りすることに意義があります。あくまで各家の自主性に任されており、江戸時代末から今日まで、自然に受け継がれてきました。しかし、近年では高齢化や転出に伴い、この風習を続けることが困難になりつつあります。また、番条では次世代を担う子ども達の数が減っているという現状もあります。このように、番条のお大師さんを守り続けるためには、さまざまな課題があります。しかし、いずれにせよ、番条のお大師さんという独特の風習は、記録に値するものであり、後世に語り継がれるべきものだと思います。