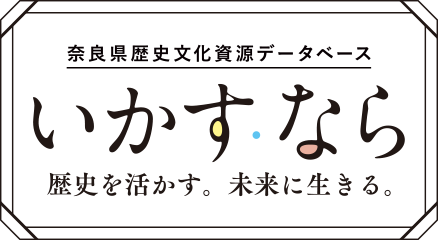達磨寺方丈 だるまじほうじょう
記入年月日 2023/04/10



- 所在地
- 奈良県北葛城郡王寺町本町2丁目1番40号
- 区分
- 建造物 | 宗教建築
- 指定内容
- 県指定有形文化財
※各歴史文化資源へのご訪問の際は公開日・公開時間・料金等を別途ご確認ください。
- 歴史文化資源の概要
- 平成元年(1989年)3月10日付けで県指定有形文化財に指定されました。3室2列の禅宗方丈の基本形からなります。屋根は本瓦葺で、西面が入母屋造、東面が切妻造と非対称なのが特徴です。棟札から建立は寛文7年(1667年)で、京都の工匠によって建てられたことが明らかです。建立されてから350年以上が経過し、建物全体が傾いていたため、平成29年度から令和2年度にかけて半解体のよる保存修理工事が行われました。昭和初期までは、町指定文化財の木造千手観音坐像が方丈の仏壇に安置されていました。奈良県では本格的な方丈建築が少ないなか、建立当初の形式がよく保存されている点で貴重です。
- 地域にとって大切な歴史文化資源である、その理由
- 聖徳太子とのゆかりが深い王寺町のなかでも、とくに達磨寺は太子との関係が色濃いといえます。達磨寺には国・県・町の指定文化財が多く所有され、王寺町の歴史文化を代表する寺院です。
そうしたなかでも達磨寺方丈は、達磨寺の唯一の歴史的建造物であり、禅宗寺院が少ない奈良県において優れた方丈建築が残されていることも大切な歴史文化資源である理由です。
- 「記紀・万葉集」との関連とその概要
- 『日本書紀』推古天皇21年(613年)12月条に、聖徳太子が飢人と出会い、助け、埋葬したところ、その飢人の遺体が消えてなくなったとされる片岡飢人伝説があります。のちに飢人が達磨大師の化身とされて達磨寺が開基されました。
また、『万葉集』巻3-415には、聖徳太子が死した旅人を悲しんで作ったという歌が収載されており、片岡飢人伝説との関連が指摘されています。
- 当資源と関連する歴史上の人物とその概要
- 伝承によれば、達磨寺方丈は慶長10年(1605年)に豊臣秀頼・片桐且元によって建立されたとされています。今の方丈は寛文7年(1667)の建立ですが、秀頼・且元は当該期に多くの寺社を再建しており、付近では法隆寺の慶長大修理にも関わっていることから、寛文7年までは彼らが建立した達磨寺方丈が存在した可能性も考えられます。
- 当資源と関連する文献史料
- 慶長12年(1607年)に達磨寺の崇厳が著した「達磨禅師興衰伝略記」(達磨寺所蔵)に、慶長10年(1605年)12月、豊臣秀頼と片桐且元が方丈を再建し、本堂に当たる開山塔を修補したことが記されています。また、平成29年度からの達磨寺方丈保存修理工事を契機に、秀頼が檀越で且元が奉行となって造営された本堂(開山塔)の棟札が発見されました。
- 問い合わせ先
- 片岡山 達磨寺
- 電話番号
- 0745-31-2341
掲載されております歴史文化資源の情報は、その歴史文化資源が地域にとって大切であると考えておられる市町村、所有者、地域の方々により作成いただいたものです。
見解・学説等の相違については、ご了承ください。